webinar
ウェビナー
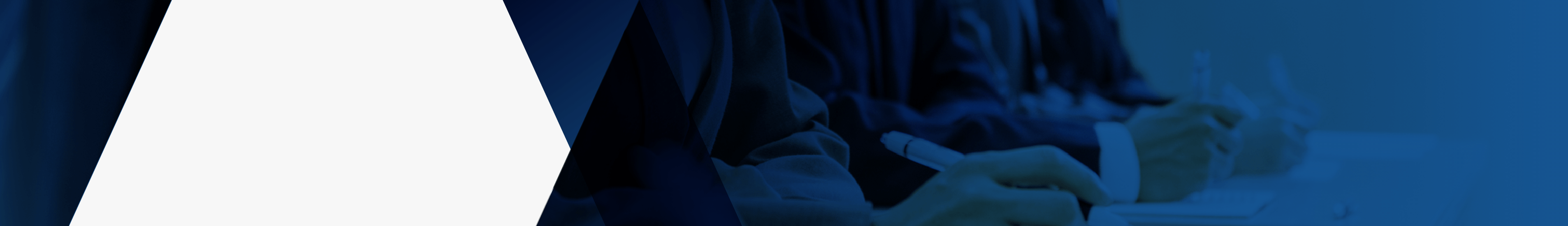
最強の意思決定

今回のWebinarでは、スタンフォードで学び、マッキンゼー等での実践経験を通じて練り上げられた『最強の意思決定 メンバーの知恵を錬成する実践手法』の著者である籠屋邦夫氏にご登場いただき、衆知錬成の意思決定の技法のエッセンスを凝縮したお話をしていただきます。
中計再策定の議論や不確実性の高い状況下での投資計画判断など、様々な場面でご活用いただける『衆知錬成の意思決定』の技法を是非、この機会にご覧ください。
衆知『錬成』の真逆:衆知『雲散』の「あるある」状況(前半)
働き方改革にグローバル化と、現在のビジネスでは大きな変化が目白押しです。この困難な時代を乗り切るべく、ディシジョンマインド社の代表取締役である籠屋邦夫氏が考案した概念が「衆知錬成」の理論です。
「衆知(≒多くの人々が持つ知恵)」を集めた上で、それを練り上げることで何十倍、何百倍もの価値を引き出す、新たな意思決定のモデルです。
ところが現在の企業では? マネジメントの現場では衆知を集めるどころではありません。むしろ「雲散」しています。よい例となるのが、某電気メーカー会社の課長の体験でしょう。今から10数年前、この課長は重要な提案をした際に役員一同から集中砲火を浴びて評価を悪化させてしまいました。
これは、世の会社員がよく体験する場面でもあります。しかし役員も各自は有能なはず。その英知を集めて最良の意思決定&最良の行動選択を実践するプロセスがあるはず。籠屋氏はそう解説します。
衆知『錬成』の真逆:衆知『雲散』の「あるある」状況(後半)
現在の企業では嘆かわしいことに、社員一同が持つ貴重な衆知が活かされずに雲散してばかりです。
過剰な被害者意識や責任回避願望の発露から、部下を混乱に陥れたり意思決定を遅らせたり事業計画の進行を妨げたり……と、衆知雲散が組織にもたらすダメージは幅広いものです。
経営を著しく阻害するこれらの厄介な課題を深く理解するために、籠屋氏は分析を重ねてユニークな病名を4タイプ考案しました。この結果、誰にとっても強く共感できる解説が実現していて必聴です。
衆知錬成の4ステップ
各社員が持つ貴重な衆知を活かすには? それを決定する最適な理論も籠屋氏は、4段階に分けてわかりやすく解説してくださいます。
個々の自助努力を推進する「独力・力強化」、そして上司と部下の関係を改善する「衆知活性化」を通じて、組織内を「烏合の衆」の状態から脱却させます。
その後に待っているプロセスは、「衆知実体化」および「衆知構造化」へのアプローチです。意見のすれ違いが絶えない中でも、円滑なコミュニケーションと議論のレベルアップが実現します。
各部署のトップや管理職、さらに末端の社員一人ひとりまで、社内のすべてのもつ知識・スキルや経験値の有効化と、企業内の人間関係を好転させ事業目的に向けての団結、その2行為を現実のものにすること。これこそが籠屋氏の提唱する「衆知錬成の実践方法論」を活用した場合の醍醐味です。
衆知構造化の道具立て
各社員が育ててきた有効な衆知を、組織において無駄なく活用するには、どんなディシジョンマネジメントが望ましいでしょうか? この点でも籠屋氏は、具体的な方法論を確立しています。
まず「ビジョン・ステートメント」を通して、事業の目的に関する各社員の認識のズレを防ぎます。次に「フォース・フィールド・ダイアグラム」という、論点の洗い出しを行う作業に臨みます。建設的な意思決定に円滑に進める点が特色です。
企業の戦略構想をさらに的確に立てるため、出すべき結論や検討すべき課題を絞り出す「ディシジョン・ヒエラルキー」の実施も外せません。
考えられる選択肢を全体で認識する「ストラテジーテーブル」の作業を経て、最後に「バリュー・トレードオフ表」を利用して事業の成功・失敗を分ける要因を洗い出します。これらのプロセスを通じて、行動に出る前に自然と「儲ける仕掛け」の作成と「儲かる仕組み」の理解が促進されます。
