leadership-insight
リーダーシップインサイト
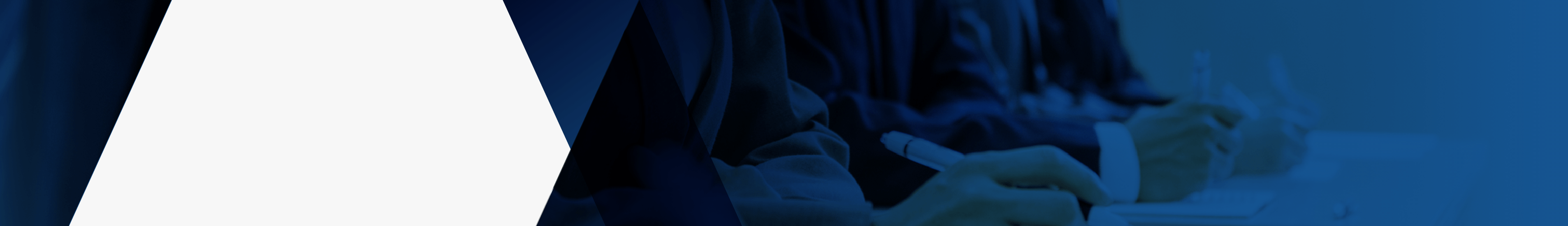
- ホーム
- リーダーシップインサイト
- 変化・変革をもたらすリーダーとは|アンラーニングとチャレンジし続けることの重要性
変化・変革をもたらすリーダーとは|アンラーニングとチャレンジし続けることの重要性

Veeva Japan株式会社
SENIOR DIRECTOR, COMMERCIAL CSM
山下 篤志 さん
目次
「VUCAの時代」と象徴されるように、世の中が複雑かつ不確実に変化し、予測困難とされる現代。企業がこの時代を生き抜き成果につなげるためには、自他に変化・変革をもたらすことのできるリーダーの存在が欠かせません。今回は、Veeva Japan株式会社においてCommercial CSMの責任者としてVeeva製品の活用支援を推進されている「山下篤志さん」にお話を伺います。
山下さんは、プログラマーおよびシステムエンジニア、ITコンサルタントとしてのご活躍、アストラゼネカ株式会社でのVeeva CRM導入や数々の専門チーム発足、そしてVeeva Japan株式会社での新たな挑戦など、ご自身や企業に対して様々な変化・変革をもたらしてこられました。
こうした変化・変革は、どのようなチャレンジやリーダーシップによって実現されたのか、背景にあるご経験やマインドに迫ります。さらに立場や世代を問わないコミュニケーションの重要ポイント、自分自身が変化し続けて楽しむことの必要性、部下の育成やマネジメントのコツ、チェンジマネジメントを実現させるポイントなど、今回も弊社独自の観点からアプローチしています。
変化・変革を求められる時代を生き抜き、成果につなげるための気づきとヒントを得られる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
山下 篤志 さん略歴
プログラマー・システムエンジニアとしてシステム設計・開発に携わったのち、コンサルティングファームに移り、ITコンサルタントとしてヘルスケアを含めた様々な業種のシステムプロジェクトに従事。前職の製薬会社では、日本へのVeeva CRM導入プロジェクトをリードし、プロジェクト後はVeeva活用の推進を担当するとともに、デジタルマーケティングやデータマネージメント、アドバンスドアナリティクスといった専門チームをリードし、多くのメンバーとともにオムニチャネルの促進にも尽力。現在はVeeva JapanのCommercial CSM (Customer Success Management)の責任者として、Veeva製品導入企業様の活用支援を推進している。
これまでのキャリアと転機
ーまずはこれまでのキャリアを教えていただけますでしょうか。
 大学では文学部でしたが、将来性を見据えてソフトウェア・エンジニアリング方面へ進もうと考えたんです。卒業後はソフトウェアハウスへ就職して、自分の基礎となるプログラマーやシステムエンジニアの経験を積みます。約3年間勤めましたが「お客様が実際にどう思っているかを直接聞いて理解したい」という思いがあり、コンサルティングファームへ転職しました。
大学では文学部でしたが、将来性を見据えてソフトウェア・エンジニアリング方面へ進もうと考えたんです。卒業後はソフトウェアハウスへ就職して、自分の基礎となるプログラマーやシステムエンジニアの経験を積みます。約3年間勤めましたが「お客様が実際にどう思っているかを直接聞いて理解したい」という思いがあり、コンサルティングファームへ転職しました。
そこから約5年にわたって、大手各社等に向けてプログラミングに関する導入コンサルティングに携わります。ただプロジェクト終了と同時に「さよなら」となり「成功したかまで見届けられない」といった思いや、当時のワークライフバランスなどを考慮して事業会社への転職を決意しました。
アストラゼネカへ入社後は、情報システム部で経理システムなどに携わっていたのですが、5年くらいしてデジタルマーケティングを立ち上げる時に声がかかったんです。そこで私のキャリアというか、流れが変わったと思います。デジタルマーケティンググループに所属して、医療関係者向けのいろいろなデジタルマーケティング、デジタルプロモーションを手がけるようになりました。
2014年には製薬業界ではグローバルスタンダードともいえるCRMソフトウェアである「Veeva CRM」を導入するにあたり、プロジェクトマネジメント兼リーダーを任されることになったんです。
その後、デジタルマーケティングとCRMを併せたCRMマーケティング部や、データがどんどん膨らむことを受けて高度な分析ができるチームも結成。さらにオムニチャネルをリードする部隊とあわせて、フィールドサポートグループも東京と大阪の2拠点で立ち上げました。もともと、CRMを発足させたときは3名だったんですけど、最終的には社員だけで30名程になりました。
そして、デジタルマーケティングからCRMを一つの会社でつくるところまではできたので、今度はそれを色々な企業へも広げたいという思いからVeevaへの転職を決意して、今に至ります。現在は、カスタマーサクセスマネジメントという部門をリードしています。Veeva製品を導入された企業が、さらに上手く活用いただくためのサポートを行う部門です。
Veevaの魅力・ユニークさとは?
ー山下さんが思うVeevaの魅力は何でしょうか?
Veevaがユニークだなと思うところは、まず人のハイヤリング(採用)ですね。Veevaは、採用活動を非常に重視して全社で取り組んでいるんです。候補者の方のジョブヒストリーやスキルはもちろんのこと、企業カルチャーとのマッチングをとても大切にしています。
あとはカルチャーフィットですね。候補者の方の「なぜVeevaなのか?」を理解するようにしています。これはハイヤリングの時に限らず、入社してからもこの「なぜVeevaなのか?」を求められる場面は多くあって、自分の中で「なぜVeeva で働くのだろう」と反復して考えることになります。
Veevaのバリューである「Do the right thing(正しいことをする)、Customer Success(顧客の成功)、Employee Success(従業員の成功)、Speed(スピード)」の4つへの共感は前提です。その上で「自分にとってCustomer Successってなんだろう」や、「Do the right thingしているかな」などを、Veeva全社員が「なぜVeevaなのか?」の視点でしっかり考えているのは、おもしろいなと。
ーカルチャーやマインドセットを維持していくための「しくみ」はあるのでしょうか。
四半期ごとの「カンパニーコール」では、冒頭で必ずCEOのピーターから全員向けにバリューやビジョンの話をします。その後に意見交換を行うんです。バリューに紐付いて戦略が落ちてくるので、筋が通っているなと感じています。
私の中でも「なぜVeevaなのか?」が、ずっと変わらないことはないんです。今は「ネットワークを広げてヘルスケア業界に対して一石を投じたい」という思いで、その土俵として様々な製薬企業様にVeevaを通じたネットワークを張っています。
ー他にも山下さんが思うVeevaのユニークさはありますか?
 カスタマーサクセスをひとつの部門として立ち上げている点は、ユニークだと思いますね。企業様には「せっかくVeevaを入れているんですから」という視点で、さらに上手く活用いただくことで貢献したいと思っています。
カスタマーサクセスをひとつの部門として立ち上げている点は、ユニークだと思いますね。企業様には「せっかくVeevaを入れているんですから」という視点で、さらに上手く活用いただくことで貢献したいと思っています。
あとは共通のプラットフォームを広げている点はユニークかなと思ってます。広げ方に関しても、やみくもではなくてトレンドに沿って広げているんです。
例えば、医療関係者間で「この情報が分かりやすかった、見てみて」というのをシェアしていきたいわけです。こうした部分で製薬企業から出した資料を他のドクターにも展開していただくような流れやチャネルをつくろうとしています。
他にもVeevaとしては治験やR&Dに関するソリューションを出しているのですが、コロナ禍で治験をする患者さんとのコミュニケーションが難しくなっているところにも注力しています。
環境の変化や市場の動き、色々なお客様からのフィードバックを反映してソリューションを成長させることで、お客様のビジネスの成長につなげていく。このように連動させていることもユニークな点ではないでしょうか。
飽くなきチャレンジの背景にあるもの
ーずっと飽くなきチャレンジを続けられてきて、今度は社内のソリューションだけでなく、世の中全体にVeevaでできることを広めていこうと。どんどん壮大になってきている感じがしますね。
世の中全てを変えるのは難しいと思いますが、これまでを振り返って私自身が「ツイていたな」と思うのが、新しい部門を立ち上げる時に上司に恵まれていたことです。
「こういう部門にしたいんだ」と言ったら、「あ、いいんじゃないの」という流れでした。当時の上司はフランス人で、特有の気質のようなものもあったのかも知れませんが。
「なんでそれが必要なんだ?」という質問に対して説明をして、新しい部門やグループを立ち上げる。新たな人材が必要な時には「こういう人材を雇用したい、なぜなら-」という説明を経てOKをもらう。こうした経験は仕事のどのような場面でも活かせると思っています。
また今後に関しては、様々な製薬企業の方とデジタルマーケティングに関する情報交換を行うなかで、各社がやりたいことには共通する部分があると感じています。そこで、Veevaという一つの共通プラットフォームで最適化していくのは有効だと考えました。ヘルスケアに特化してはいるのですが「何かおもしろいことをしたい」というのがあったんです。
ー山下さんは、ワクワクすることがお好きなんですか。
 もちろん嫌いではありませんが、自分では慎重な方だと思っていますね。
もちろん嫌いではありませんが、自分では慎重な方だと思っていますね。
高校の頃は割と目立ちたがり屋でしたが、大学のときはそこまで色々なことをやったわけではなく、大学生活の半分くらいは新聞配達センターのバイトで、学費を賄っていました。根が真面目なのか分からないんですが、授業はちゃんと出ていて、ほとんど「優」だったのは事実です。
なのでワクワクを目指して突飛なことをしてきたわけではないですが、「とりあえずやってみよう」の精神でフットワークは軽い方だと思います。
立場や世代等を問わないコミュニケーションの重要ポイント
ー上司を巻き込んでいくときの山下さんなりのリーダーとしてのポイントはありますか?
上司の“クセ”ってそれぞれ違うので、その辺を把握してからでないと行かないようにしています。要はジャブを打って、どう返されるかを見てから次に行くようなイメージです。
例えば、先ほどのフランス人の上司ですと、アイデアがすごい上にシステム的な細かいところも熟知している人なので、ちょっとポイントがずれると「いや、それはノーだ」と言うんですね。つまり、そこに合致さえすれば「いいよ」という話になるんです。
全体像が合っているかを先に聞いた上で細かく詰めていく方が良い上司もいれば、詳細からボトムアップで説明していき最終的にSo Whatでベネフィットにつながることを示す方が良い上司もいます。
社外に対しては当然「顧客一人ひとりにあわせましょう」という話ですが、社内に対しても一人ひとりに合わせた言い方や説明の順番を工夫しないと上手く巻き込めないと思います。
ー世代間ギャップは企業の課題として挙がりがちですが、やはり「相手が何を知りたいか」「相手はどういう思考プロセスか」を押さえていくのが大切ということでしょうか。
そうですね。おそらく今後は、オムニチャネルでも議論になっていきますが、X世代・Y世代・Z世代など色んな世代間のギャップを埋めながら顧客や社員を育てていくのは非常に難易度が高いです。いずれにしても「相手が何を欲しているのか」の起点は必須だと思います。
積極的に受け入れてチャレンジする姿勢
ーキャリアが進むにあたって身につけた新たな学びや能力などはありますか?
 正直なところ分からないというか、色々な経験を積んでいつの間にかできるようになっていく感覚です。先ほどの「ワクワク」につながるんですけど、今回のインタビューのように、「様々なお願いごとを基本的には断らない」ようにしています。
正直なところ分からないというか、色々な経験を積んでいつの間にかできるようになっていく感覚です。先ほどの「ワクワク」につながるんですけど、今回のインタビューのように、「様々なお願いごとを基本的には断らない」ようにしています。
例えば、あるアカデミーの勉強会でお話しさせていただいているんですが、そこで「マーケティング4.0が製薬企業で通じるのか」という議題でディスカッションをすることになりまして・・・。
ーすごいお題ですね!
話すべき内容や、考えておくべきことなど沢山あるので、勉強し直すにあたって「もっとこう説明した方がわかりやすいんじゃないか」など、どんどん最適化されていくんです。振り返って思うことですが、こうした機会にチャレンジする姿勢は大切にしてきました。
ー依頼ごとに対して自分にとってのメリットを考えるのではなく、山下さんのように機会が来たんだから受け入れるという姿勢、その分岐は何なのでしょうか。
例えば、今回のインタビューもそうですけど、今までに出演されている方とつながって話せる機会が得られるかも知れないとか、可能性を広げていくと自分のキャリアにもつながるんじゃないのか、と前向きに捉えるようにしています。
あとは「これはおもしろそうだな!」と思って食いついていくのもいいんじゃないかなと思いますね。
リーダーとしてアンラーニングは必要?あえて捨てるべきもの
ーこれまでのキャリアをお伺いすると、やっぱりアンラーニング(学習棄却)が必要だった部分もあったのではないかと思いますが、今まで自分で捨てたものは何かありますか。
管理職になる時に「細かい部分を自分でしてしまうところ」は捨てなければなりませんでしたね。
例えば、アストラゼネカの頃に協力会社がつくったシステムを詳細にチェックし始めると、本来見るべきところが疎かになるということがありました。そこで、協力会社には「その結果だけ持ってほしい」という旨を伝えました。
捨てるというよりも「自分はもうこういう視点でしか見ませんよ」と宣言するようにしています。
ただ一番つらかったのは、デジタルマーケティングの細かな部分の話や「こんな新しいサービスがあるんだったらこう使えるかもね」みたいな議論をメンバーに任せないといけなかったことですね。新サービスの議論は楽しいのですが、リーダーの自分が一つひとつは入っていくことはできないので。
なので私からは、会社として部門としての方向性を示した上で「おもしろい話があったら持ってきて」というスタンスに変えていきました。
ーつまり「共通するスキル」はアンラーニングする必要はない。ただ役職が変わるにつれて、捨てなくてはならないものがあるという話ですね。
おそらく考え方のコアになっているのは、一番最初のソフトウェア会社で学んだものだと思います。プラットフォームをつくるときは、ロジカルシンキングになると感じています。大きく分岐があるのを見て、ロジックを描かなければなりません。そのアウトプットが「公表」だったりするわけです。システムもそうあるべきだと思っていて「ロジックを成り立たせる」というコアは同じです。
ですので、ソフトウェア会社、コンサルティングファーム、アストラゼネカ、Veevaと変わっても、考え方のコアは変わらないんだと思います。
部下の育成とマネジメントでおさえるべきポイント
ー部下の育成やマネジメントに関して、山下さんが心がけていることやコツ、ポイントなどはございますか。
 一番メンバーが多かったアストラゼネカの時を思い返すと、もともと素地がある人を選んでいる前提はありますが、スタッフとして会社の中で「こうなりたいんだ」とメンバー全員に伝えることはとても重要だと思っています。
一番メンバーが多かったアストラゼネカの時を思い返すと、もともと素地がある人を選んでいる前提はありますが、スタッフとして会社の中で「こうなりたいんだ」とメンバー全員に伝えることはとても重要だと思っています。
「自分はこうしたいんだ」という思いをちゃんと伝えて「足りないものは何だっけ?」という話をするんです。さらに「あなたは今ここができていて助かっているよ。ただ、ここの発展は必要だと感じているんだけど、どう思う?」のように、要は組織からブレークダウンして、足りない部分をきちんと補ってもらうことも重要だと考えています。
ただ、なかには「いやいや、技術を突き詰めたいんだ」という思いのメンバーもいました。それは私としてはありがたいなと思っているので、まずは「それはわかりました」「あなたはこうしたいんですよね」としっかり理解を示します。その上で「だけど、会社への貢献として表現しないと、あなたの価値を上手く示せないよ」という話をしなければなりません。
もちろん会社は自己実現の場だと思っています。一方で“カンパニー”には仲間という考え方もあると思うので、仲間つまりは会社としての実現も両立させるべきだと考えているんです。
「あなたはこれをしたいんだよね。であれば、会社としてもあなたにやってほしいことがあるはず」これが両方カチッとはまるのがベストですが、実際はなかなか難しい。まさにバランスの話ですので可能な範囲で調整しながら、コミュニケーションを図っています。
変革に不可欠なチェンジマネジメントを実現するためのポイント
ーチェンジマネジメントのご経験について、やはり全社や部署単位での改革・改変などはビックチェンジなわけですが、それを受け入れてもらう・行動を変えてもらうための山下さんなりのアプローチがあればお教えください。
チェンジマネジメントの際は、もちろんベネフィットは全て示しつつ、「ピンポイントで困る部分は何ですか」「そこはどうやったら和らぐと思いますか」を一緒に聞きにいくということが必要だと考えています。
例えば営業の支店を廃止するという話が出た時も「困りますよね」「わかります」という共感から入ります。ただし決定事項なので、「仕方ないじゃないですか」とは言わないですけど「何が一番困りますか」「何か良いアイデアないですか」と尋ねます。
Veeva CRM導入の時もそうだったのですが、「もう導入されることは決まっています」という時には「課題は何ですか」と聞いて「では課題に対してこうやって解決しますね」ではなく、「どうやったら解決できると思いますか」のアイデアまでもらいにいくというところは、チェンジマネジメントには欠かせないと思います。
過去の自分からのエール
ー山下さんの“軸”をかたちづくっているもの、ご自分のよりどころになっているものは何でしょうか。
 難しいですね。というのも「気がついたら今に至っている」というところなので。ただ困難などに直面した時には「過去にもっとすごいチャレンジしてきているはず」というふうに思っています。先ほどの新聞配達のアルバイトもそうなんですけど「金沢の冬の新聞配達」って半端ないんですね。除雪車が6時くらいに動き出すんですけど、新聞は3時半くらいから配り始めるんです。30〜40㎝積もるなかバイクなんて動かないので、何キロも結局引きずって歩きながら配っていました。
難しいですね。というのも「気がついたら今に至っている」というところなので。ただ困難などに直面した時には「過去にもっとすごいチャレンジしてきているはず」というふうに思っています。先ほどの新聞配達のアルバイトもそうなんですけど「金沢の冬の新聞配達」って半端ないんですね。除雪車が6時くらいに動き出すんですけど、新聞は3時半くらいから配り始めるんです。30〜40㎝積もるなかバイクなんて動かないので、何キロも結局引きずって歩きながら配っていました。
ですので、けっこう自分で「あんなことをやっていたしな」と思うようにしていますね。
他にもソフトウェア会社からコンサルファームに移って私もまだビギナーだった頃、役員に説明をしなければならない場面があったんです。そこで「こうしないとだめです」という話をしたんですけど、役員からきっぱりと「ノー」と言われたんです。その時に完全に頭が真っ白になってしまって。
今でもトラウマですが、それ以降は顧客の方にバンと言われるという経験はしていないんです。おそらく自分のハードルが上がっているんです、説明する範囲が広いとか。
過去のチャレンジに失敗しても成功しても、それを糧に成長していて、新たにチャレンジする時には「過去にあんなことをしてきているし、大丈夫!」というのが、芯にあるんじゃないないかなと思います。
変化の時代を生きるリーダーへ伝えたいこと
ー山下さんから、これからリーダーを目指す方へ伝えたいことはありますか。
チャレンジの話は先ほどしたので別の話を。これはアストラゼネカのときに営業のトップの方が熱弁されていたのですが「外に出ろ」という話ですね。自分の中に、会社の中に閉じこもっていると、思っていることもできない。
例えば、私もデジタルマーケティングの会とか色々な会に呼んでいただいていますが、そういうネットワーキングがあったら必ず出席します。これは損得の話とかではなくて、そこで知り合った方から新しいソリューションを一緒につくりませんか、という話をいただけるんですね。
他にも、外でつながりができた企業様に後から大いに助けられるケースもありました。コロナ禍でMRは紙を持っていけないとなった時、ある企業様が手がけているオンデマンドプリントを活用しましょう、そうするとMRの手間も省けますよねとなったんです。
そういう風に、後から意味を持つつながりも、その時はわからないんです。ですので外に出てネットワーキングを広げておくのは大切です。
あとは、思いついたら「メモに残すこと」。
昔からの習慣で、例えば電車でボーっと外を眺めていても思いついたら直ぐに書き留めています。メモの習慣を続けていると、機転が利くようになったり、人に説明をするときに例え話がしやすくなったり、物事のつながりに気づきやすくなったりするんです。
CMを見ている時でも「いつか使えるかも」と思ったらメモに残しておく、こうしたちょっとした積み重ねが未来につながっていくことは、意識しておくと良いと思います。
―プログラマーやシステムエンジニアのご経験に基づくロジカルな思考、一方でどのような機会も前向きに受け止めてチャレンジされる姿勢。山下さんがもたれている「静と動」の絶妙なバランスによってこれまでの成果がもたらされたのだと感じました。きっとこれからも様々なご経験を活かしつつ新たなチャレンジを続けることで、世の中が必要とする変化・変革をもたらされるのだと思います。素敵なお話をありがとうございました。
