leadership-insight
リーダーシップインサイト
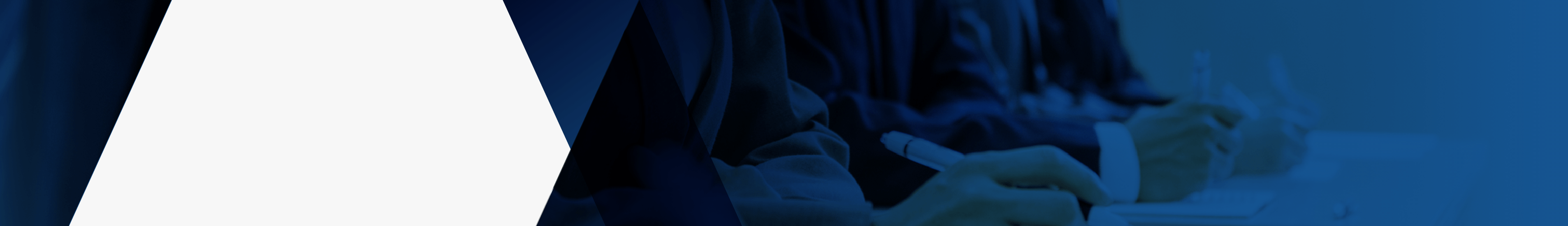
- ホーム
- リーダーシップインサイト
- HRBPの役割をどのように設定するのか
HRBPの役割をどのように設定するのか

カゴメ株式会社CHRO有沢様とともに参加した勉強会での気づき
2020年9月16日、CHO協会主催で、カゴメ株式会社のCHROの有沢さんとともに、日本におけるHRBPのあり方を考える勉強会(WEBINAR)を行いました。
最初に私から、「米国におけるHRBPの役割と職務」と題して、米国企業のHRBPがどのような職務を実施しているか、またその職務を実行するためにHRBPがどのようなトレーニングを受けているか、事例をお話しした後で、有沢様より、カゴメにおけるHRBP制度について詳細を説明していただき、それらを受けて参加者全員でこれから日本企業のHRBP制度はどうあるべきかを考えるという流れでした。
この勉強会でいくつか気づきがあったので、それをみなさまと共有したいと思います。
① HRBPの役割を考えるためのフレームワークがない
今回の勉強会には20社の企業の人事部の方々も参加してくださいました。すでにHRBPを導入している企業もあれば、まさに導入を検討している企業など、HRBP制度に関心をもっていらっしゃる方々ばかりです。しかしながら、「HRBPの役割をどのように定めるのか、明確な考え方がない」「どのような役割定義にするか迷っている」という会社が大半でした。
なぜHRBPの仕事の範囲を決められないか。これには2つの要素が関わっていると感じました。
一つ目は、大変失礼ながら、HRBPとして何をしたいか(どのように会社に貢献したいのか)明快な意思がないように感じた、ということ。もう一つは、そもそも自社の組織や人材にどのような問題があるのか、現状を診断するための道具立てを持っていらっしゃらないのではないか、ということです。
HRBPはその名の通り、経営や事業部門長の実現したいことを組織、人材面からサポートすることが役割で、そこまではみなさん共通のイメージをもっていらっしゃるのですが、より具体的には何をどこまでサポートしたいのか、そこを決めきれていないと感じました。
自社の人材を深く理解して、経営者や事業部門長が、「こんなことを実現したいんだけど、誰がそれを担えるだろうか?」と聞かれたときに、「それなら今○○部にいるXさんが適任ですね。」とか「それが担える人材は我が社には現在いません。すぐにヘッドハンターなどを使って候補者を挙げさせます。」と答えられるようになりたいのか、経営者や事業部門長が成長戦略を考え始める場にも常に同席して、「これから当社は間違いなくこの方向に進む。とすればこのような人材を揃えておく必要があるし、制度もこのように変えていく必要がある。今からいろいろ準備しておこう。」と先取りしていきたいのか、あるいはもっと別ことをしたいのか、何をどこまでやりたいのかで職務内容は全く異なります。当たり前ですが、どこまでやるのが「正しい」という決まりがあるわけではないので、結局のところ人事部長やHRBPヘッドがどこまでやりたいか、という意思の問題です。
一方で、もし自社の組織や人材について現状を(できれば網羅的に)診断するツールがあって、それによってどこが問題かが明確になっていれば、その問題を解決することをHRBPの役割にする、ということも可能なはずですが、そのような診断ツールを持っていらっしゃる会社も少ないのではないかと感じました。気をつけなければならないのは、多くの企業で実施されているエンゲージメント調査や従業員満足度調査が、HRBPの役割を考える「組織診断ツール」として適切かどうかです。
もちろん、これらの調査結果によって、組織が抱えている問題のある側面を明らかにしてくれているとは思いますが、エンゲージメント調査の結果を改善したり、従業員満足度をあげることが、経営者、とくに上場企業の経営者なら誰でも求めているであろう業績改善につながるのか、と言われれば甚だ疑問があると感じています。
HRBPが最終的に経営者や事業部門長にとって戦略実現のパートナーになりたいのであれば、戦略の実現をKGIにしたときに、今の組織や人材が「effective」なのかどうかを判定する診断ツールである必要があります。
どこまでやりたいのか意思が明確でなく、自社の組織課題も明確につかみ切れていない中で、他社の事例をいくら集めても、結局はなにも決められないのではないかと感じました。
② カゴメの有沢様の取り組みはまさにアラインメントである
それとは対照的に、カゴメの有沢様のやってきたことには明確な意思と「軸」がありました。
有沢様がどのようなことに取り組んで来られたかについては<事業部人事(HRビジネスパートナー)の役割は、経営と現場をつなぐこと 有沢正人氏(カゴメCHO)×中原淳氏(立教大学教授)対談>に詳しく載っているので、そちらを読んでみて頂きたいのですが、人事部門の方々は、「カゴメがキャリアコンサルティング制度を導入した」、という部分だけにスポットライトを当てがちです。でも今回お話しを聞いて、有沢様の取り組みは、事業戦略と現場の方向性を揃える「アラインメント」を実現するための緻密で戦略的な取り組みであることがよくわかりました。
人事部門ではなく、事業部門からベテラン社員、しかもそれぞれの部門で一目置かれている社員を引き抜いてきて、キャリアコンサルタントの資格を取らせ、社員一人ひとりと面談をさせて、誰が何をしたいのかを把握する。現場がわかっている人でないと、だれも本音を話さないという考えのもと、キャリアコンサルタントは事業部門から抜擢する。さらに有沢さんの信条として、「べき論では人は動かない。したいことをさせるのが一番だ。」とお考えがあるようで、とにかく一人ひとりの社員が何をしたいのか、を聞いてそれをサポートすることに徹する。しかもお話しを伺うと、このキャリアコンサルタントは、時に経営陣の意向を伝える役割も果たしているようで、「この間、社長は・・・とおっしゃったけど、・・・・といことを言いたかったんだと思うよ。」と各部署の現場の人にもわかりやすい言葉に言い換えて話をするそうなのです。そうやって経営陣の意思を現場に浸透させながら、それを実現したいと思っている人が誰なのかを把握してつなぎ合わせていく。会社が実現したいことと、個人がやりたいことを、重ね合わせているのです。HRBPなどという言葉は一切使わず、“キャリアコンサルタント”という社員から受け入れられやすい形式をとりながら、戦略と現場のアラインメントをしっかり実現していらっしゃる、ということがお話を聞いていてよくわかりました。
そして何よりも大事なのが、このようなアラインメント活動が破綻しないよう、ジョブグレードを統一し、各ポジションに求められるアカウンタビリティ、役割、報酬、求められる知識・スキル・経験も可視化して透明化することで、チャレンジ意欲を引き出しているということです。
その仕事にチャレンジしたいなら、こういう知識や経験も求められるよ、だからこんな風に取り組んでみたらどうだい、とキャリアコンサルタントが言える下地をしっかり整えているところに「凄さ」を感じました。
HRBPの役割が何であるべきか、正解はありません。結局、
- 自社を成長させるために、今の自社における問題・課題はなにか
- その中で自分はどの問題・課題を解決に取り組みたいのか
この2つをはっきりさせない限り何も生まれないということを改めて認識するよい機会を得ることができました。HRBPの創設を考えている皆様、この2つが明確になっていますでしょうか?
※有沢様の肩書は勉強会当時のものです。
■インヴィニオのHRBP/アラインメント・リーダー養成講座のご案内はこちらから
