leadership-insight
リーダーシップインサイト
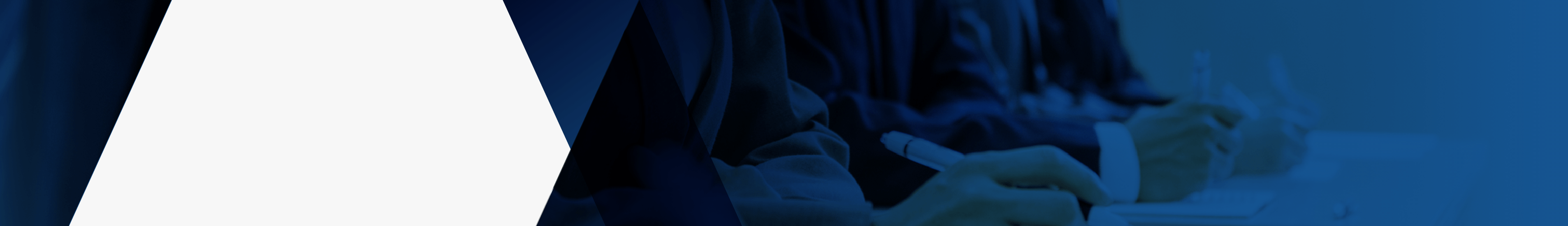
- ホーム
- リーダーシップインサイト
- 従業員の帰属意識とモチベーションを高めるコツ|組織との目標整合
従業員の帰属意識とモチベーションを高めるコツ|組織との目標整合

目次
従業員の帰属意識とモチベーションを高めることは、すべての組織において重要かつ優先すべき課題です。
一方で「自社の従業員は帰属意識が低い気がする」「組織全体のモチベーションをどうすれば底上げできるか分からない」と悩むリーダーも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、鍵となる「組織と従業員の目標整合」を中心に、従業員の帰属意識とモチベーションを高めるコツについて紹介します。本記事にて紹介する内容は、世界を代表するビジネス人材育成のプロであるCCL(Center for Creative Leadership)が、綿密なリサーチおよび支援実績を基に導き出したものですので、ぜひ参考にしてください。
従業員の帰属意識とモチベーションを高めるために組織と目標を合わせる
従業員の帰属意識とモチベーションを高めるには、従業員と組織の目標を整合させることが大切です。そのためのポイントを以下で紹介します。
目標が有する「パワー」を信じる
従業員にそれぞれの実力を発揮させるためには、外発的動機づけ(報酬などの外的インセンティブに基づく行動)よりも、内発的動機づけ(個人的な満足感や楽しみに基づく行動)がより強力であることが証明されています。
目的意識を強く持った状態で仕事に取り組む従業員は、自然と高い充実感が得られ、より積極的に仕事に取り組むようになります。組織は、従業員のキャリアプランの各段階において意図を持った目標を設定することにより、目標の持つ力を引き出すことができます。
これにより、組織は従業員個人の目標と会社の価値観を関連付けし、従業員が自らの目標を特定し実現する手助けを行えるのです。
このコンセプトを具現化した例として、インドに本社を置くグローバルIT企業TCSのオリエンテーション・プログラムが挙げられます。TCSの新入従業員は、最初の顧客として非営利団体とペアを組みます。これにより新入従業員は給与の範囲を超えて「より大きな」目標の達成に貢献しているのだと理解できるようになります。
同社はその他にも、非営利団体の理事会への参加、無償プロジェクトでの陣頭指揮、コミュニティサービスの主導など、従業員のキャリアを通じてさまざまな活動に参加することを推奨しています。こうした同社は「従業員は一度きりのボランティア活動をはるかに超えた、より大きな目標を実現させる自由を有するべきである」を理念として掲げています。
リーダーが組織の中で目標を与え、帰属意識やモチベーションを育む方法は数多くありますが、その出発点は「目標に対して従業員が自信を持ち、変化を起こす可能性がある」と信じることです。
目標は「本心」と結びつくものとする
組織の目標は、組織のウェブサイトや受付の壁に掲げられる社是よりも、はるかに大きく重要です。目標を実現する第一歩はインサイド・アウト型のアプローチであり、リーダーたちが有言実行することで示されます。
ただし、漠然とした目標は「グリーンウォッシュ(見せかけの環境対策)」や「パーパスウォッシュ(行動が伴わない目標設定)」に転換する可能性があります。グリーンウォッシュやパーパスウォッシュであることが露見されると、従業員がやる気を失い、組織がブランドイメージに取り返しのつかないダメージを被りかねません。
組織の目標とは別に、個人が「真の目標を探求する場」を提供することは、信頼関係を構築し、意欲的な従業員を確保する上で大きな役割を果たします。
組織の目標と従業員の目標が食い違う場合、人事担当者は積極的に心を開いた対話をすべきです。その結果、その従業員が他組織の目標がより自分に合うと感じ、転職する可能性もあるでしょう。これはお互いにとってプラスとなるのです。
一方、従業員の意見を聞くことで、組織の目標設定に影響を与えるケースもあります。例えば、自動車会社のベテラン従業員が、所属企業とは異なる価値観や目標を持っていれば、その会社の環境面、社会面、ガバナンス面の理念を変えるきっかけとなる可能性があります。このように、組織は自社を体現するベテラン社員の意見提供を重視し、評価しなければなりません。
目標にまつわるストーリーを示し、目標にリアリティを持たせる
目標を中心に据えたストーリー(物語)は、従業員が自分の貢献や個人の価値観を組織全体の目標と結びつけるのに役立ちます。自らがそのストーリーの中で役割を担うことを実感することで、帰属意識と一体感が育まれます。それは、各従業員がより大局的な環境の中で役割を担っているという感覚です。
組織的なストーリーテリングを実践している例として、インドのコングロマリットであるマヒンドラ・グループがあります。同グループは、「RISE」というグループの哲学にまつわる中核的な目標を設定し、目標に関連した全てのイニシアティブの活動の中心に据えています。
RISE哲学では、企業は「コミュニティ」を、個人、仲間、社会グループ、地球など、すべてのステークホルダーを含む最も広い意味で解釈しています。RISEは、コングロマリット内の各事業グループが、それぞれの目標達成に向けてどのように「活動すべき」なのかを定義する指針となります。
組織における目標を組織のストーリーの「主人公」として掲げることで、従業員たちは、所属部門の垣根を超え、目標達成につながる仕事を重要視し、決められた目標を達成するという団結のもと、部門を越えて協力し合えるようになります。組織の目標に基づく原則に沿って行動することで、さまざまなレベルの従業員が、すべてのステークホルダーに利益をもたらす意思決定を行えるようになるのです。
従業員の帰属意識とモチベーションを高めるために
従業員の帰属意識とモチベーションを高め、個人のコミットメントを真に引き出すには、目標が目に見えるかたちで優先事項に組み込まれなければなりません。つまり、目標が従業員個人の願望や課題と感情的に関連付けられている必要があるのです。
従業員の目標と組織の目標が合致することで、各従業員は自身の貢献がより大きな目標達成に繋がることを感じるようになり、その結果、全体の帰属意識とモチベーションが育まれていきます。
弊社「株式会社インヴィニオ」は人材育成のプロとして、学びを知識や能力のレベルに留まらせるのではなく「実力」へと昇華させることにコミットします。事業の成果として表れるように、人や組織が保有する「成果を生み出す能力」を引き上げ、引き出し、顕在化させることを重視しています。
「帰属意識やモチベーションを高めるだけでなく、しっかりと成果につなげたい」とお考えの方は、まずはこちらから気軽にお問い合わせください。
