leadership-insight
リーダーシップインサイト

- ホーム
- リーダーシップインサイト
- 研究開発者のためのビジネスマインド養成講座(その6)
研究開発者のためのビジネスマインド養成講座(その6)

これまで「研究開発者のためのビジネスマインド養成講座」を5回に亘り連載して参りました。第3回では、ビジネスR&Dにおいては顕在需要を捉えるだけでは不十分で、潜在需要を如何にキャッチするかが重要であることを論じました。続く第4回~第5回では、「認知的不協和の呪縛」を解き放つことで潜在需要を顕在化できるケースがかなりあることを示しました。
顧客価値の壁
潜在需要を顕在化させる上で、実はあと二つ大きな壁を乗り越える必要があります。それは「顧客価値の壁」と「価格の壁」です。今回のコラム(最終回)ではこの二つの壁についてご説明したいと思います。
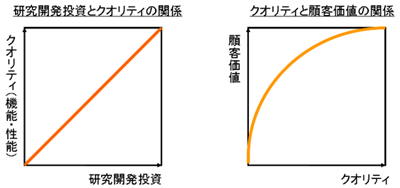 図1
図1
図1の左図は、研究開発投資とクオリティ(機能・性能)の関係を概念的に表しています。一般に技術や製品は、研究開発資源(人×金×時間)を投入すればするほど性能や機能を引き上げていくことが可能です。自動車、薄型テレビ、DVD、AV製品、デジカメ、パソコンなど、私たちの身の回りにあるハイテク製品を見まわしても、一般的に高価格(すなわちより多くの研究開発費を投入したもの)であるほどハイクオリティ(高機能、高性能)です。ところがやっかいなのは、クオリティを上げていってもそれ以上の顧客価値の向上に結びつかない天井にぶつかってしまうことです(図1の右図)。多くの消費者は、自分が欲しいレベルのクオリティが一旦満たされてしまうと、それ以上のクオリティに対する“ありがたみ”を段々感じなくなってきます。例えば車にしても、時速0から100kmまでの加速性能については高速道路に侵入する際にドライバーが実際に体感できますが、150kmから200kmへの加速性能に関しては、(少なくとも日本の道路交通法上は)体感できないゾーンに入ってしまうので顧客価値の増加は薄れると考えられます(注:実は前回のコラムで提唱した認知的価値の議論からすると、体感できないことにも価値を感じる消費者が存在する可能性は確かにあります。特に日本では、周りの目を気にする国民性のせいなのか、認知的価値を重視する消費者が米国などに比べてかなり多いと思われます。この議論は機会があればいずれコラムで取り上げてみたいと思いますので、ここではひとまず「実感的価値が優先する」ということでご了解頂ければと思います)。
価格が手ごろになって爆発的に売れている薄型テレビについても同様の現象が起きています。家電量販店に並ぶ薄型テレビ(液晶或いはプラズマ)をよく見ると、“ハイビジョン”と“フルスペックハイビジョン”という二種類のハイビジョン対応製品があることに気付きます。ハイビジョンと表記されている製品は解像度が横1,366ドット×縦768ドットであるのに対して、フルスペックハイビジョンの方は横1,920ドット×縦1,080ドットの解像度です。このハイビジョンとフルスペックハイビジョンの違いに関して、今ネット上では大激論が交わされています。「正式なハイビジョンの規格“1080i”では、1,920×1,080ドットの解像度をハイビジョンと定めている。だから1,366×768ドットをハイビジョンと呼ぶのはそもそもおかしいのだ!」、「1,920×1,080ドットこそが本物のハイビジョンなのだから、フルスペックなどという余分な枕詞は要らない。単純にハイビジョンと呼べばいいのだ!」、「えっ、そしたら1,366×768ドットの方は何て呼べばいいのさ。“偽ハイビジョン”とでも呼べって言うの!」・・・。技術的な違いの詳細は割愛しますが(興味のある方は是非ネットで“フルスペックハイビジョン”で検索してみて下さい)、簡単に言うと番組製作・放送システムの技術上の問題のために、フルスペックハイビジョンの解像度で映像を放映することが困難であったため、便宜的に映像を間引いて送信したものを“ハイビジョン”と呼んだことが原因で起きた混乱のようです。「どちらが正当なハイビジョンか」という宗教論争は議論好きの方々にお任せするとして、より大切な問題は顧客がフルスペックハイビジョンとハイビジョンの映像の違いを本当に認識できるのか、フルスペックハイビジョンの方がハイビジョンよりも明らかにキレイと感じるのか、という点です。「私には明らかに違いが分かる」という目の肥えた消費者の方もおられるようですが、家電量販店での顧客の様子や店員の方々の対応ぶりを見る限り、一般的な消費者にとってハイビジョンとフルスペックハイビジョンの違いを見分けるのはそれほど容易ではなさそうです。業界関係の方から聞いた噂ですが、ある家電メーカーは量販店にルーペ(拡大鏡)を大量に配ったそうです。顧客がハイビジョンとフルスペックハイビジョンのどちらにしようか迷っていたら、すかさず「お客様、是非このルーペで画面を拡大してご覧下さい。フルスペックハイビジョンのきめ細かさが一目瞭然です」というセールストークをして下さいという訳です。大辞林(三省堂)によれば、一目瞭然とは「ひと目見てはっきりわかること」を指すそうですが、今後は「ただし、ルーペなどで拡大した場合も可」と注記すべきかも知れません(笑)。しかし、メーカーにとっては笑い話どころではないのも事実です。せっかく苦労を重ねてフルスペックハイビジョンを開発したのに、顧客がその真価を理解できないとあってはルーペを配りたくもなるのも当然かも知れません。正にこれこそが「顧客価値の壁」ということになります。
価格の壁
では次に「価格の壁」について説明します。
 図2
図2
図2の横軸は顧客価値/価格(=顧客価値を価格で割った値)、縦軸は顧客ニーズ(=その製品への欲求)の強さを表しています。横軸の右に行けば行くほど「価格のわりに顧客価値が高い」ことを意味します。顧客価値/価格が上昇すれば一般的に顧客ニーズも高まるはずですが、ビジネスの観点からすれば「お金を払ってでも欲しいと思う」かどうかが問題になります。図2では、顧客ニーズの強さをレベル0「あっても無くても同じレベル」、レベル1「在る方がややましなレベル」、レベル2「在るといいなレベル」、レベル3「是非とも欲しいレベル」、レベル4「無いと困るレベル」の5段階に区分しています。すると顧客が買ってくれるか否かの境界線は、レベル2とレベル3の境目に存在すると考えられます。つまり「在るといいな」のレベルでは、顧客はお金を払ってまで手に入れようとはしない、ということになります。新技術・新製品を手掛ける研究開発者は、特にこの点に十分な注意が必要です。革新的な製品を初めて上市した時点では、1)それまでに要した研究開発コストが製品価格に転嫁されてしまう、2)製造技術が未確立で歩留まりが悪い、3)数が出ないので材料コスト、部品コストが高い、などの理由によって高額の価格設定にならざるを得ません。そうなると、革新性ゆえに“顧客価値”自体は高いものになったとしても、顧客価値/価格で見るとかなり低くなってしまい、結果的にレベル2以下の顧客ニーズに留まってしまう可能性があります。これでは、どんなに素晴らしい技術・製品であったとしてもさっぱり売れない憂き目に会います。この障壁を「価格の壁」と呼ぶことにします。
“マビカショック”とまで言われた、ソニーの電子スチルカメラ(=デジカメの原型)“マビカ”も「価格の壁」に阻まれた製品の一つです。1981年にソニーが試作したマビカは、「写真は銀塩フィルムで撮影するもの」という常識を根底から覆す画期的製品で、当時の新聞は一斉に「これで銀塩フィルムは世の中から無くなる!」と書きたてました。しかしこの試作機は230万円もしたため、ロサンゼルスオリンピックの取材用として新聞社などに採用されただけでした。その後ソニーはさらに技術開発を進め、1988年に家庭用マビカの1号機MVC-C1を発売します。オートストロボ、高速連写、セルフタイマーなどの機能を備えた優れものでしたが、20万画素で64,000円もしたために一般消費者に広く普及するまでには至りませんでした。デジカメが本格的にブレイクするのはマビカショックから10年以上後の1990年代後半になってからで、面白いことにインターネットの普及と深く関連しています。1995年にマイクロソフトがWindows95を発売し、ブラウザーソフトIE(Internet Explorer)で誰でもホームページを閲覧できるようになると、少しITに詳しいお父さんたちが我が子の可愛い写真をデジカメでバシバシ撮って、自作のホームページに載せ友人や知人に自慢するブームが起きました。このHP作成ブームがデジカメの普及に一気に火を点けたのでした。
松下電工が開発した家庭用フィットネス機器“JOBA(ジョーバ)”も、幾多の「価格の壁」を乗り越えてブレイクした商品です。ジョーバは医学博士の木村哲彦氏が松下電工に、「ヨーロッパで普及している乗馬療法を日本でも広めたい。そのために乗馬ロボットを作れないか?」という相談をしたことが始まりでした。この依頼を受けて松下電工のエンジニアは馬の動きを徹底的に研究することから始めました。実際の馬の動きをモーションキャプチャすることで複雑な鞍の動きを3次元解析し、それを6本のシリンダーを利用することで、6自由度の動作として再現。特に常足(なみあし)、速足(はやあし)、駆足(かけあし)の3つの動作を忠実に再現することに成功しました。こうして1995年ついに6本足の乗馬ロボットが誕生したのです。しかしこのジョーバ1号機は、機構が非常に複雑であったため値段が2000万円にもなってしまい、一部の医療施設に納入されるに留まりました。その後松下電工は機構の単純化や部品の標準化を徹底的に推進し、二桁のコストダウンに成功してようやく一般家庭への普及に漕ぎ着けたのでした。
以上で全6話に亘ったコラム「研究開発者のためのビジネスマインド養成講座」は一旦完了です。本連載を最後まで読んで下さった研究開発者の皆さんが、世界を変える画期的な技術と製品を生み出すことを祈念しつつ。
参考文献:
