leadership-insight
リーダーシップインサイト
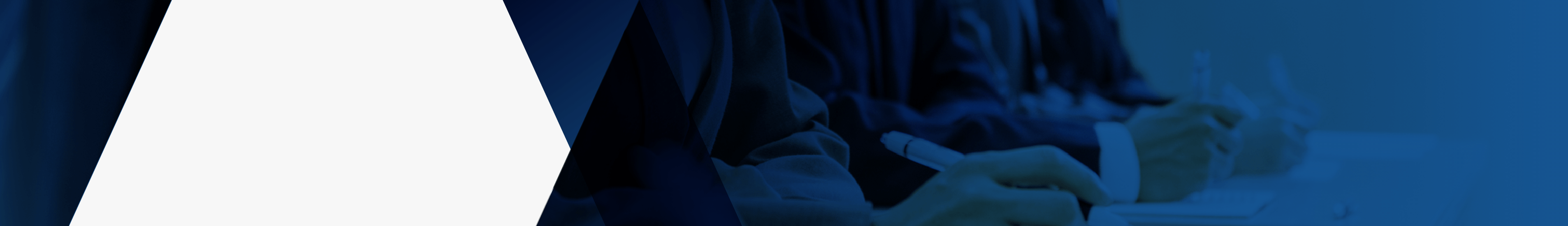
- ホーム
- リーダーシップインサイト
- 研究開発者のためのビジネスマインド養成講座(その4)
研究開発者のためのビジネスマインド養成講座(その4)

認知的不協和の呪縛
前回のコラムで、「認知的不協和の呪縛」が潜在需要を健在化させる上での隘路(ボトルネック)になっており、呪縛からユーザーを解放することで潜在需要を顕在需要に変えられる可能性がある、という私の仮説を提起しました。この仮説に関して、いくつか具体的な事例を見ながらさらに考察を進めていくことにします。
事例1:味覚の保守性
最初に、前回のコラムで触れた大塚製薬のポカリスエットの例ですが、事前の市場調査(試飲会)では酷評されたのに、実際に発売してみたら売れるようになった(=需要が顕在化した)のはなぜなのでしょうか?実は味覚というのは嗅覚と並んで、人間にとって身の安全を守る上で最も大切な感覚です。口に入れたときに少しでも違和感があったら、人間は即座にそれを吐き出そうとします。味覚は、人体にとって毒かも知れないものを摂取しないための大切な安全装置なのです。そのため「自分がいつも慣れ親しんでいる味との違和感」(=認知的不協和)には非常に敏感です。日本を訪れた外国人が「テンプラ、オイシイ」、「オオトロ、ダイスキ」とは言うものの、納豆、生卵、味噌汁、うに等はどうしても駄目という人が多いのも、“味覚の保守性”(=味覚に関する認知的不協和の呪縛)によるところが大きいためと考えられます。つまりポカリスエットの市場調査では、この味覚の保守性の問題にモロに直面してしまった事が不評の原因だったということになります。ポカリスエットが最初に発売されたのは1980年。当時は日本人の味覚がまだ「濃い目の味」を好む傾向が強く、清涼飲料も甘みの強いものが主流でした。ポカリスエットは発売後もしばらく苦戦が続き、味覚面ですぐには消費者には受け入れられなかったようです。さらに「運動中に水分を摂ってはいけない!」という当時の誤ったスポーツ根性論も、ポカリスエットの普及を妨げた一因だったようです。しかし経済・社会の成熟と共に日本人の味覚も変わり、清涼飲料も薄味のものが好まれるようになってポカリスエットは市民権を得ることができました。またスポーツ科学が発達し「運動中は適度な水分補給が必要」という正しい常識が広まったことも、ポカリスエットの販売を後押しする結果となりました(メデタシ、メデタシ)。
事例2:精神的葛藤
さてポカリスエットのエピソードは、人間の五感に関する「認知的不協和の呪縛」の事例ですが、次にご紹介するのは“精神的葛藤”と呼ぶのが相応しい「認知的不協和の呪縛」の例です。スイスに本拠を置くグローバル企業ネスレが1938年、「ネスカフェ」の名称で知られるインスタントコーヒーを初めて発売した時のこと。ネスレの当初の予想では「主婦は毎朝、朝食の準備や子供の支度で忙しい」⇒「インスタントコーヒーならドリップ式でコーヒーを入れる手間が不要になり、主婦は喜んで買ってくれる」はずだったのですが、予想に反して売れ行きがすこぶる悪い。不可解に思ったネスレがマーケットリサーチで消費者心理を調べたところ、意外な事実が判明しました。なんと消費者(主婦)は、「インスタントコーヒーを買ったりすると、(ドリップ式が面倒くさいと思っている)怠け者と周囲から見られるのではないか」と懸念していたのです。そこでネスレは早速広告戦略を変えて「活動的で働き者の主婦こそがインスタントコーヒーを賢く活用する」ことを訴えるようにしました。その結果消費者心理が変わり、インスタントコーヒーの普及が進むようになったそうです。この事例では、インスタントコーヒーの購買層である主婦の心に、“手間要らずで便利”⇔“怠け者”(と人から思われる)という「認知的不協和の呪縛」(=精神的葛藤)が生じ、その結果需要の顕在化が妨げられたと言えます。
事例3:視覚的イメージ
三番目の事例として、「認知的不協和の呪縛」を技術が見事に解き放ったケースを取り上げます。と言ってもかなり古い話なのですが、江戸時代の豪商18人の成功物語を収めた「江戸300年 大商人の知恵」(童門冬二著、講談社プラスアルファ新書)に、「ふとんの西川」の礎を築いた二代目西川甚五郎の逸話が出てきます。甚五郎の実家は近江商人でしたが彼は成功を夢見て単身江戸に渡り、徳川家康が江戸に幕府を開設したわずか12年後の1615年、日本橋に畳表の店を開きます。当初甚五郎は江戸の建設ブームに乗り畳表の商売で一儲けしますが、やがて建設ブームもひと段落すると新たなビジネスチャンスを模索し始めます。時節は夏、甚五郎は町人たちのニーズを知るために銭湯巡りや長屋歩きにせっせと精を出します。そこで甚五郎の耳に飛び込んできたのは「ああ暑い、暑い」、「でも扉を開けっぱなしにすると蚊が入ってくるしね~」、「蚊に刺されるとかゆくてたまらないよな~」と言った町人同士の会話でした。この会話を聞いて甚五郎にはピンとアイデアが閃きました。「そうだ、蚊帳を作って売ろう!」。幸い実家(西川屋本店)がある近江八幡周辺では、麻糸の原料となる「からむし」(イラクサ科)が豊富に取れます。甚五郎は早速本店に連絡し、「からむし」で蚊帳を作らせて江戸に持ち込みました。しかしどうしたことか、彼が額に汗して実施した市場調査結果に反し、蚊帳の売れゆきはさっぱりです。甚五郎には全く理由が分かりません。そうこうして迎えた翌年の夏、甚五郎は江戸から近江に向かう旅の道中で、長屋住まいの町人たちの会話を再び思い出し、販売不振の原因にはたと思い当たります。「ああ、暑くて寝苦しい。もう少し涼しかったらいいのに。気分だけでも何とか涼しくなれないものかなあ」真夏の夜、長屋の住人たちは蚊に苛まれていただけでなく、暑さによる寝苦しさにも大いに悩まされていたのです。ところが甚五郎の売り出した蚊帳は、からむしの素材そのままの薄暗い茶色。見た目にいかにも暑苦しくて、これでは誰も買う気にならない。そこで甚五郎は「見た目に涼しい色ならば売れるのではないか」と即座に閃き、初夏や木陰の涼しさを連想させる緑色に蚊帳を染めることを思い立ちます。早速近江の本店と掛け合い、腕のいい染色職人に依頼して目にも涼やかな緑色に蚊帳を染め「涼しい蚊帳」と名付けて売り出しました。結果は大当たりで、やがて江戸の名物の一つにまで数えられるほどの成功を収めました。このケースでは、蚊帳に関して“蚊に食われず快適”⇔“(見た目には)暑苦しい”という認知的不協和が生じ、その結果需要の顕在化が妨げられたと考えられます。この事例で注目したいのは、技術(=涼やかな緑色に染めるという優れた染色技術)が認知的不協和を解消するのに大いに力を発揮したという点です。何分江戸時代の事なのでハイテクという程の技術ではありませんが、的確なテクノロジーの活用が潜在需要を顕在化させたという点では特筆すべき先行事例であると思います。
事例4:技術者としての心理的違和感
さて最後に、技術が「認知的不協和の呪縛」を解放した新しい事例をご紹介します。最近家電量販店などに行くと、充電できる乾電池「エネループ」をよく目にするのではないかと思います。「エネループ」は三洋電機が開発した画期的なニッケル水素電池で、乾電池(単3、単4)と全く同じ形状・使い勝手でありながら、何度でも充電できるという優れものです。まさにエコ、リサイクルが求められる現代社会のニーズにマッチした製品と言えますが、「エネループ」が誕生するためには消費者のみならず、開発者自身が「認知的不協和の呪縛」を乗り越える必要がありました。小型のニッケル水素電池は元々デジカメ向けの用途が中心で、2001年頃からデジカメの販売急増と共に急激に売上を伸ばしました。しかし2003年頃を境に、ニッケル水素電池の将来に突如暗雲が垂れこめます。リチウムイオン電池の躍進です。リチウムイオン電池はニッケル水素電池よりもエネルギー密度が高く、小型・軽量化が容易です。当時デジカメは軽量化・薄型化をめぐってメーカーが凌ぎを削っていた時代で、そのためデジカメメーカーは一斉にニッケル水素電池からリチウムイオン電池にシフトしました。その結果ニッケル水素電池市場は急速に縮小し始め、三洋電機の充電池事業は苦境に陥ります。強い危機意識を持った三洋電機の事業担当者は、消費者に対するニーズ調査、意識調査を徹底的に行いました。その結果判明したのは、「どこで売っているのか分からない」、「そもそも存在自体知らない」という存在感の薄さでした。デジカメ用途がリチウムイオン電池に置き換えられた結果、ニッケル水素電池を消費者が使う機会は激減。また消費者からすると、「乾電池については、そもそも使い捨て」という長年の常識があり、特段それで困ることも無かったので、「充電式乾電池」の必要性を特に意識することはありませんでした。つまりニッケル水素電池は、事実上顕在需要から潜在需要へと逆戻りしていた訳です。一方三洋電機の開発者の側にも「技術に関する認知的不協和」に縛られるジレンマがありました。ニッケル水素電池がデジカメ用途に使われていた時には、開発者はひたすら電池の高容量化を目指していました。少しでも高容量化して電池を小型化することが、デジカメ用途で生き残るための至上命題だったからです。ところが「充電式乾電池」を作ろうということになると、今度は(高容量化ではなく)自己放電の抑制が大問題になってきます。電池というのは、使わなくても時間の経過と共に徐々に放電してしまうことが避けられませんが、当時のニッケル水素電池は乾電池に比べて自己放電特性が大きく劣っており、乾電池と同じ使い勝手で使えるレベルではありませんでした。この時に開発者の心を呪縛したのは、「高容量化と自己放電抑制のトレードオフ(二律背反)」の問題でした。自己放電特性を改善するためには高容量化を犠牲にする必要があるのですが、高容量化を至上命題としてきた当時の開発者にとっては、高容量化を犠牲にして自己放電特性を改善するという逆説的アプローチには、技術者としての心理的違和感(=技術の方向感に対する認知的不協和の呪縛)がありました。しかし事業リーダーのイニシアチブの下、そうした心理的違和感も乗り越え遂に実用に耐える充電式乾電池「エネループ」の開発に成功するや、エコ・リサイクルといった時代のニーズと相まってたちどころにヒット商品になったのです。この事例は、「認知的不協和の呪縛」は消費者だけを襲うものではなく、しばしば開発者側の発想を妨げるボトルネックにもなるということを教えてくれるものです。
以上4つの事例について「認知的不協和の呪縛」の様々なパターンと、その解放による潜在需要の顕在化プロセスを見てきました。次回のコラムでは、本コラムでの事例分析を踏まえて、需要顕在化検討のための新たなフレームワークについてご提案したいと思います。(インヴィニオ取締役 高井正美)
参考文献:
「そこが知りたい家電の新技術 三洋電機・エネループ担当者に聞くヒットの理由」
「そこが知りたい家電の新技術 三洋電機「エネループ」【技術編】」
「マーケティングは消費者に勝てるか?」(ルディー和子著、ダイヤモンド社、2005年)
「江戸300年 大商人の知恵」(童門冬二著、講談社プラスアルファ新書、2004年)
