leadership-insight
リーダーシップインサイト
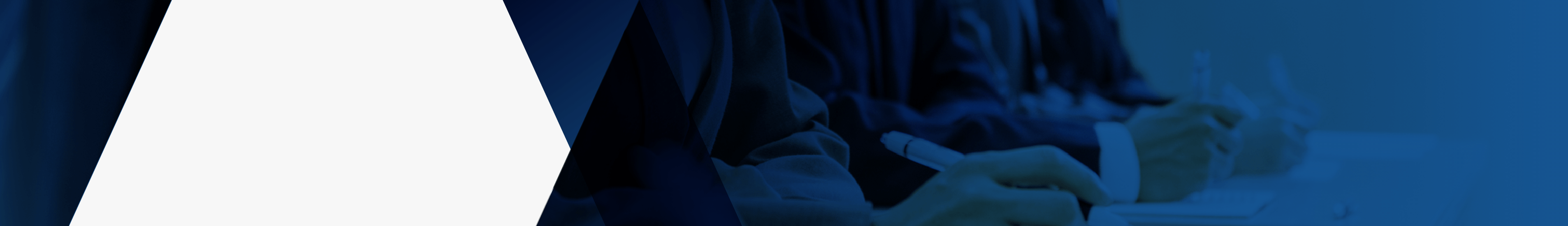
- ホーム
- リーダーシップインサイト
- 雇用の質について考える~慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授 高橋 俊介
雇用の質について考える~慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授 高橋 俊介

雇用の質の低い企業の問題は
社会的視点で雇用について論じるときは、今まで雇用の量的側面が重視されてきた。その代表が失業率であり有効求人倍率だ。新卒の就職状況も内定率などが議論の中心だった。しかし最近雇用の質についての議論が盛んになってきた。その代表が「ブラック企業問題」だろう。いわゆる人を使い捨てにする、雇用の質のきわめて低い企業の問題だ。質を数値で把握しようとした試みの一つが、ここ数年厚生労働省が公表している、大学卒高校卒の業種別3年以内離職率である。この数字が発表されたときには、大きな衝撃があった。大学卒は3年で3割、高校卒は5割といった数字はよく語られてきたが、その数字が業界ごとにここまで違うかという驚きである。
例えば観光や宿泊業とか介護福祉などの分野は以前から離職率が高いと考えられてきたが、それが証明された形だ。観光宿泊業は、まず勤務地が僻地に多い。人が休んでいるとき休めない。さらには賃金水準が低い。星野リゾートの星野社長によれば、日本の宿泊業の生産性は欧米に比べて著しく低く、それが原因で賃金などの労働条件が高くなりにくい。その原因の一つは日本は休暇が集中し、100日黒字265日赤字というのが典型的宿泊施設の実態らしい。繁閑差が激しく、在庫の持てないこのような業界では、当然雇用も非正規を多く抱えざるを得ない。
一方介護福祉は、繁閑差がそこまで大きいわけではないが、24時間勤務などの問題はある。それ以上にキャリアステップが描きにくい、IT化などによる生産性向上が遅れている、収入が国の制度に依存するなど、社会的必要性は高くやりがいがあっても、雇用の質が上がりにくい。これだけ待機児童問題が深刻でも、保育士は労働条件が良くないので常に人手不足だ。
「働き甲斐」と「働きやすさ」
以上述べてきたのは、実は雇用の質でも働きやすさの部分である。これはもちろん改善されなければならない。一方でサービス業化する日本における人材育成の重要性については、すでにこのコラムでも述べたが、やりがいや成長は雇用の質でも、働きがいに属する部分である。
現在様々な分野で人材確保が難しくなってきている。労働条件などの働きやすさは人材確保するうえで非常に重要な項目であることは間違いない。さらには女性の育児休職明けの復職率を上げるための柔軟な働き方、働き方改革による残業の削減、有給休暇取得率の向上などの働きやすさ改善は、継続雇用促進の意味も大きい。
こういう時代、人材確保のための最大のポイントは離職率を低くすることにほかならない。離職率が高いと、こういう時代その補充が簡単に見つからない。そのしわ寄せが現場に行く。その結果労働条件が低下し、補充採用ができる前にさらなる離職を招く。そうなると顧客サービスが低下し、ひいては業容縮小をせざるを得なくなる。一方で離職率が低くなれば採用必要数が減るので、人を選ぶこともできる。
離職率を下げるためにはほかにどんなことが重要なのか。私は実は働きやすさもさることながら、若い人たちの場合は働き甲斐がより大きい要素のように思う。確かに新卒入社早々から、「ワークライフバランス」とか言って、ほどほどの働き方に固執する若者の話は最近よく耳にするが、それは本人と会社双方にとって大きな問題だ。長時間労働は問題だというが、長時間労働には良いものと悪いものがある。悪いものの代表が「ワーカホリズム型長時間労働」だ。能力不足で仕事がうまくいかないストレスと不安を抱え、それを払しょくするために長時間労働に依存するというのは一番まずい。若者のメンタルによく見られるパターンだ。それに対して、私が「プロジェクトX型長時間労働」と呼ぶ、やりがいがあり面白いので思わず長く働いてしまう長時間労働は、人を成長させる。あの有名番組の主人公たちが、当時9時5時で仕事を終えていたとは到底思えない。
仕事にのめりこんで成長する期間が若いうちに持てるのは、そのあとの仕事人生に大きなプラスとなる。それなしに若いうちから生涯9時5時で淡々と仕事をする人生で、豊かな人生になるのだろうか。おそらく今の時代環境変化に振り回されて、ひどい目にあうのではないか。会社にとっても社員の成長なくして仕事の高付加価値化、ビジネスモデルの進化はあり得ない。また私が行った20代の若者の調査では、今の会社に今後長く勤めたいと思うかは、成長実感と成長予感双方と高い相関がある。つまり振り返っての成長実感と、今後数年にわたってさらに成長できそうと思えることが、若者の離職防止には大きな影響を与える。
スターバックスコーヒーのアルバイト離職率が非常に低いのも、バイトの4段階の成長ステップに基づいた、非正規育成システムが機能しているからに他ならない。昔私がインタビューした、あるスタバのアルバイトの女性は、「初めにこの店に来たとき、バイトなのに3年以上勤めている人が何人もいるのにびっくりしたが、自分が成長して、新人のコーチ役などの成長ステップを進んでいくうちに、自分も気づいたら3年になりました。」と話していた。
一方で一生仕事人間会社人間では、人生の豊かさや人間としての成長は得られないし、家族との絆も維持できない。特に家族を持ち、子供ができ、親が高齢化し、そのような人生の進展に伴って、働きやすさはますます重要になる。
しかし働きやすさの向上は、離職率の低下などとりあえずの人材確保には一定の効果はあろうが、短期的には会社業績と相反しやすい。一方働きがいは成長による付加価値向上など、中期的長期的に会社業績に貢献する。例えば沖縄に多いBPOでは、今や単純なコールセンター業務では収益を生むことが難しくなってきている。より付加価値の高い事務業務技術業務などへのステップアップが不可避だが、そのためには人材育成が欠かせない。
つまり雇用の質は、若い人たちに対しては働きやすさ以上に、やりがいや成長などの働きがいを重視し、人材育成に注力すべきだ。新人が失意のうちに早期離職し、自己肯定観を得られないまま、そのあとも職を転々とすれば、社会的な損失だ。社会に出て3年以内に適職感を得られるか、つまりこの仕事が向いている、続けていけそうだという肯定観を得られるかどうかは、その人の生涯の職業的発達や生涯所得に大いに影響を与えるという分析もある。
そしてキャリアを積んでいく中で、働きやすさが重要になってくる。働きがいでビジネスの付加価値を上げ生産性を上げて、それとともに働きやすさ向上を進めていくことが求められる。成長や自己肯定観なしに人材を使い捨てにする若年者早期離職率の高い会社は、社会に負担をかけているわけだから、私は雇用保険料を高く設定するなどの経済合理性のつじつまを合わせる施策をするべきだと思う。その収入で、雇用の質向上を努力する企業への補助を賄うような社会的サイクルがなければ、公害を垂れ流しながら利益を上げる企業を許すのと同じ理屈になってしまう。
安易に安価な非正規人材に頼った戦略で、生産性の悪いビジネスを続けてきた会社は、今や立ち行かない。こういうタイミングこそ、社会的にも雇用の質向上を促す政策や制度を政府や厚生労働省は進めてほしい。おりしも昨年12月よりストレスチェックの法律が施行された。このタイミングにもう一度雇用の質を働きやすさと働きがいの両方の視点から点検してみてはどうだろうか。
(慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授 高橋 俊介氏による寄稿)
