leadership-insight
リーダーシップインサイト
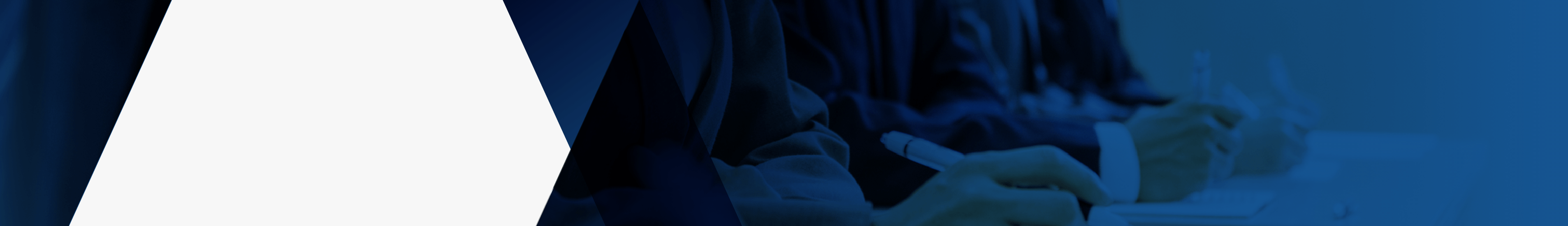
- ホーム
- リーダーシップインサイト
- 科学は人事を変えるか~慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授 高橋 俊介
科学は人事を変えるか~慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授 高橋 俊介

組織人事の科学的な視点
人事組織に関わる仕事をしている方々や経営者にとって、人と組織のマネジメントを考えるとき、その基盤となるのが、組織人事の世界観であると思う。例えばそのひとの日本人観は、人事組織のビジョン、つまり目指すべき組織の姿、大切にすべき価値観に大きく影響する。もちろん経営人事の観点からは、経営ビジョンやビジネスモデル、人材像からそれらは導き出せるということになるが、それもたった一つの正解を導くとは限らない。いくつかの選択肢の中で、どのような組織人材マネジメントのあり方を選択するかは、その人の組織人事に関わる様々な世界観が大きく影響すると考えられる。
一方で、その世界観は往々にして極めて科学的根拠に乏しい思い込みである場合も少なくない。極端な例は、「日本人は農耕民族だから集団主義なんだ」という日本人観。これは二つの意味で明らかに誤っている。まず農耕民族が集団主義とは限らない。例えばフランスは2000年以上前から定住型農耕社会を形成し、ローマ時代に「ガリア」と呼ばれたころにローマ帝国の食糧庫的な役割を果たした。そして今でも有数の農業国であり、食料自給率は120%程度もある。しかし、私もフランスの企業に勤務したことがあるからわかるが、極めつけの個人主義だ。そもそも農耕民族か狩猟民族かは、そのような人的性質とは相関がないということは、心理学的にも実証されているらしい。
さらには、後述するように、実験社会心理学の権威、北海道大学名誉教授の山岸俊男氏によれば、組織に積極的に貢献しようとするという意味では、日本人は米国人より集団主義的ではないと結論付けている。
組織人事の世界はややもすると、哲学や思想の世界、つまり人文科学的な世界で語られがちだったが、最近は経営学や経済学、つまり社会科学的な視点が重要視されるようになった。そして心理学や社会心理学、さらには哲学などが、脳神経科学や分子人類学などと結びつき始めている。これからは社会科学と自然科学の融合による世界観の形成が重要になってくるのではないかと感じている。
例えば、最新の心理学や脳神経科学の研究により、「我思う、ゆえに我あり」は明確に否定されている。我思わなくても我はあるのだ。人間の脳の知能は最低でも7つ、最高では20以上と考えられる、相互に独立した別々の知能から成り立っているらしい。IQのような知能はその一つに過ぎない。その研究がさらに進めば、社会的知性や創造的知性といった、仕事上重要な知性がどのようなものなのか、どうすればそれを向上させることができるのかが分かってくるかもしれない。
また、最新の分子人類学のDNA分析により、人類の祖先がすべてアフリカから拡散した単一祖先を持つことがはっきりした。いわゆる人種差別の原点でもある人類の複数同時起源説は明確に否定されている。出アフリカの後の人類がどのように世界に散り、進化していったかが、DNA分析で明らかになりつつある。その中で我々日本人のイメージも変わりつつあるようだ。この中で縄文人と弥生人という単純化された過去の考え方は否定され、日本人のルーツが思いのほか多様性に富んでおり、それらの多様な人たちが混ざり合い同居し合ってきたのが日本民族らしい。むしろ中国大陸では異民族同士の争いなので、根絶やしにされたり追い払われたりして、多様性が失われる歴史があったらしい。
ユーラシア大陸の端の島国だからこそ、多様な人たちが最後にたどりついた場所で、平和な共存が行われてきたという考え方も成り立つ。
人事を社会科学・自然科学・そして歴史的視点を加えて考える
前述した山岸教授は社会心理学で、特に実験による実証を重ね、さらには認知科学など、より自然科学的な分野との学際的研究をされてきた。その山岸教授の著書に、「日本の安心はなぜ消えたのか」、「安心社会から信頼社会へ」などがある。ぜひ一読をお勧めしたい。日本は内向き集団での安心社会を強化してきたことで、戦争には負けたものの、戦後輸出型製造業を主体に高度成長を果たした。英国などヨーロッパの先進国は、自国市場の飽和を、外の機会を取り込むことで、つまり植民地を市場化することで、経済的成長を続けた。その時に重要だったのは外向きの信頼社会の形成だったのだ。
英国のインド統治が、少ない人数でどのように効率的に行われたか、それが日本の戦前の植民地支配とどう異なったか、そしてその統治の主役となったインド高等文官がどのように選抜されどのように教育されたのか。「英国紳士の植民地統治」という本に詳しい。
さらには、戦後の名著の一つと私が思っている、梅棹忠夫氏の「文明の生態史観」による、日本と西ヨーロッパの第一地域と、その中間の第2地域という考え方は、この安心社会と信頼社会の枠組み、さらには分子人類学による人類の拡散の系譜とも大いに関係する。つまり山岸氏によれば、中国のような第2地域では、民族同士の抗争と専制君主制により、信頼社会はもちろん、安心社会も形成されなかった。だから血のつながった親族しか信用しないということになったともいえるのだろう。一方で日本は、内集団において血のつながりと関係なく安心していられる、より大きな村社会を形成することで、騙されるといったいわゆる「取引コスト」の低減を図ってきた。長い関係の系列会社との取引を重視するのも、中根千枝氏の名著「タテ社会の人間関係」で指摘されている自前主義もこのような視点から説明可能だろう。
一方でこの内向き集団においては、誰が信用できるかという判断能力である「人間性感知能力」は重要でなく、狭い世界での相互の「人間関係感知能力」が発達するという。この村を出ては生きていけないから、この村で浮かないように注意するという意味で、出る釘にならない集団主義となる。この場合最大のリスクは、外界での新たな機会を得られないという機会損失である。機会損失が取引費用の低減というメリットを超えて大きくなった西欧では、外に出て短時間に相手が信頼できる人かどうかを見極め、またこちらも相手に信頼できる人間であることを示す能力、つまり人間性感知能力を磨く必要がある。
インドで間接統治という難しい仕事を担った高等文官に求められた最も重要な能力の一つは、多様な辺境の少数民族との信頼関係の構築であった。
これ以上様々な名著の解説をするつもりはないが、人事を人文科学ではなく、社会科学と自然科学、そして歴史的視点を加えて考えることが重要だということを申し上げたい。歴史も最新の研究で、過去の定説がひっくり返されている分野が少なくない。はるか昔大学時代に学んだ一般教養の知識や、ましてや何の根拠もない、限られた経験からの偏った自論だけをベースにして世界観を形成し、組織人事を語るのはまずいと思う。
このような様々な歴史や科学の最新の流れなども勉強しながら、組織人事の新しい時代にふさわしい世界観を議論していくような場を、今後ぜひ作っていきたいと考えている。
(慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授 高橋 俊介氏による寄稿)
