leadership-insight
リーダーシップインサイト
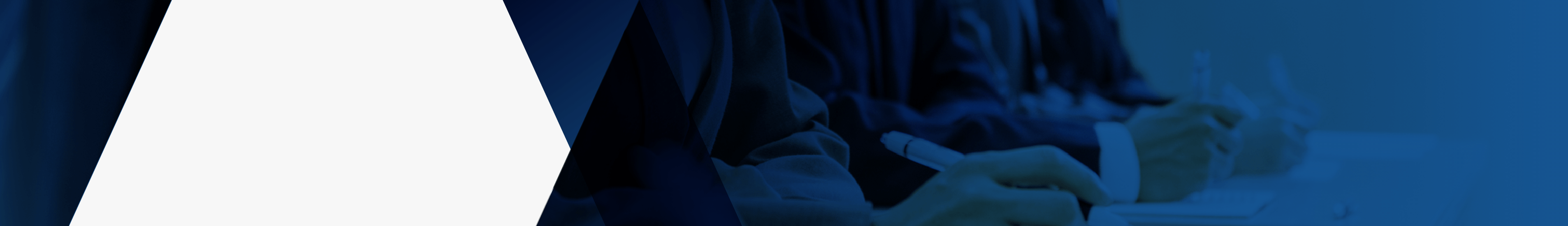
- ホーム
- リーダーシップインサイト
- 【緊急対談】人的資本経営を読み解く~中川有紀子氏に聞く
【緊急対談】人的資本経営を読み解く~中川有紀子氏に聞く

立教大学 大学院ビジネスデザイン研究科
前教授
中川 有紀子様
目次
イノベーションや企業価値を創造する源泉として「人的資本」が急速に注目を集めています。米国においてはNYSE(米国証券取引所)に上場している企業に対して、人的資本に関する情報開示が義務付けられました。開示内容はISO30414として体系立てられ、今後、機関投資家との建設的な対話の一材料として活用されていきます。
日本でも東京証券取引所の再編が行われ、プライム市場へ移行する企業は統合報告書の重要部分として人的資本の状況についての開示が求められるようになりました。
しかし、この人的資本についての開示というものは「機関投資家ないしは政府機関から求められているから行う」ものなのでしょうか?
人的資本に関する開示は「人が価値創造の源泉」という信念のもと経営陣が経営の重要イシューとしてプロアクティブにそのストーリーを語っていくもの、と立教大学大学院・前教授の中川有紀子さんは言います。
実務家としても活躍し、企業の外部取締役を経験され、なおかつアカデミアにも籍を置き、先端知見を日々深めている中川さんに「人的資本の開示」についてのお話を伺います。
(聞き手:株式会社インヴィニオ 代表取締役 土井哲)
人的資本の開示が求められている背景:アニュアルレポートや有価証券報告書との違いは?
土井(以下D):何故今、人的資本の開示が求められているのかについて簡単にご説明いただけますでしょうか。
中川氏(以下N):時系列的にお話すると、まず欧州で2020年1月に、英財務報告評議会(FRC)が人的資本に関する報告書を公表し、同年の8月米国証券取引委員会(SEC)が突然上場企業に対して「人的資本の情報開示」を義務づけると発表し、同年11月より順次人的資本の開示が始まりました。そして翌年の2021年6月日本においても外圧に呼応するかのようにコーポレート・ガバナンスコードが改訂され、人的資本の開示が原則として追加されました。
 これらの急速な展開の理由は、企業は人なり、ということです。DXもAIもSDGsもESG経営も、今色んなことが企業に求められていますけど、すべて人が実行しますので、じゃあ一体御社はこれらを実行する人財としてどういう人がいるんですか、ということをあらためて非財務情報として開示を求めてきたわけです。今まで多くの資本主義というのはBS(バランスシート)、PL(損益計算書)、CF(キャッシュフロー計算書)にみられる要するに後付けの財務情報で見て、投資家はそれぞれの企業の価値を判断していたわけです。つまりそれが成績表だったわけですが、昨年から非財務情報というものの開示を投資家が求めるようになりました。
これらの急速な展開の理由は、企業は人なり、ということです。DXもAIもSDGsもESG経営も、今色んなことが企業に求められていますけど、すべて人が実行しますので、じゃあ一体御社はこれらを実行する人財としてどういう人がいるんですか、ということをあらためて非財務情報として開示を求めてきたわけです。今まで多くの資本主義というのはBS(バランスシート)、PL(損益計算書)、CF(キャッシュフロー計算書)にみられる要するに後付けの財務情報で見て、投資家はそれぞれの企業の価値を判断していたわけです。つまりそれが成績表だったわけですが、昨年から非財務情報というものの開示を投資家が求めるようになりました。
意図としては、よりあなたの会社のポテンシャル、あなたの会社の未来はどうしていくのかというものが含まれた内容だからです。それによって、将来に投資価値上昇期待を求める機関投資家にとってみれば、この会社はほかの会社が真似できない”ケイパビリティ(capability)” (企業が全体としてもつ組織的な能力、あるいはその企業に固有の組織的な強み)を持っている会社である、すなわち、将来性がある、企業価値が上がっていく会社であるということで、株を買うわけです。他社が真似ができない”ケイパビリティ”を持っているかどうかを非財務情報で見たいという投資家の要求により、この人的資本の開示が世界中で求められているわけです。
D:突然、そういうことが出てきたというお話でしたが、市場から見ると前触れなく、本当に突然の感じだったんですか?
N:欧州では2020年1月から出ています。そのちょうど一年前ぐらい2018年にISO30414、社内外に対する人事・組織に関する情報開示のガイドライン、が出てきまして、欧州の上場企業、ドイツ銀行をはじめとする企業が2018年ごろから徐々にヒューマンキャピタルレポートというのを出すようになってきました。そこで、世界で一番大きい証券市場はニューヨークですので、その米国のSECがニューヨークで上場している企業に対して、人的資本の開示を求めてきたんですね。それが一年も経たないうちに日本に入ってきたわけです。展開の速さに驚きですね。
投資家の視点:“ケイパビリティ”がキーワード
D:ポイントとしては、さっき仰っていただいたように他の会社が真似できないようなケイパビリティを持っているかどうか、競争優位性があるかみたいなところをその情報から探っていこうということなんですね。
N:そうですね、戦略というのは、もし同業種の会社が同じ戦略を取っていれば、規模の大きいところであったり、先行者が絶対勝つわけですよ。でも実際にはそうなっていない。なぜならば、戦略が同じであっても、その戦略を実行する人間、組織が違っている。その部分は他の会社がそんな簡単に真似できないんですね。そう簡単には真似ができない”ケイパビリティ”にこそ、競争において優位性がある。戦略はいかようにも模倣でも立てられますけれど、それを実行する模倣困難な”ケイパビリティ”を持っているかどうかを投資家はみているんです。
D:今のお話を聞くと、もう一つ投資家が気にしそうなのは、市場を切り拓くような力、今の市場でいかに勝っていけるかということもある一方で、そもそも新しい市場を切り拓いていくような力というものも見ようとしているのかなと感じたんですがそういう側面もあるんでしょうか?
N:そうですね。それはよく言われるオライリー教授の”両利きの経営”ですね。深化と探索という相反する力をいかに組織の中に内包していくかの組織能力です。もちろん専門性がある人というのはどんどん深化していくわけです。でも深化だけでは、新しい市場というのは切り拓けない。その市場だけが大きく深くなっていくだけ。新しい市場を切り拓く力というのは、違う考えを持った、違う見方ができる人、いわゆるダイバーシティな人材がそこにいるかどうかというのがこの市場を切り拓く力であって探索する力であり、イノベーションなんですね。もちろんそこには摩擦がおきます。摩擦があるからこそイノベーションが起こり、新しい市場が拓かれていく。ダイバーシティが重要とされているのはそういう理由です。
D:なるほど。わかりました、ありがとうございます。まさに機関投資家はそういう観点を知りたいと考えていると思えばいいんでしょうか。
 N:そうですね、企業というのは、株主の出資によって成り立っています。所有者は株主です。経営者は株主によって委任されて経営をおこなっている。株主は当然、株の価値が上がっていくことを望んでいる。機関投資家のお客様は一般個人であったり、個人の年金基金であったり、そうした一般個人が最後のステークホルダーなわけで、機関投資家は資金の委託者に対してフューディシャリー・デューティー(受託者の忠実義務)があります。つまり、委託者に対して、より多くのリターンをださなければならないのです。当然将来価値の上がる企業に投資したいわけです。投資選別をいかにしていくか、それがBS、PL、CFだけでは本当の企業価値が把握できないという最近の動向なんですね。
N:そうですね、企業というのは、株主の出資によって成り立っています。所有者は株主です。経営者は株主によって委任されて経営をおこなっている。株主は当然、株の価値が上がっていくことを望んでいる。機関投資家のお客様は一般個人であったり、個人の年金基金であったり、そうした一般個人が最後のステークホルダーなわけで、機関投資家は資金の委託者に対してフューディシャリー・デューティー(受託者の忠実義務)があります。つまり、委託者に対して、より多くのリターンをださなければならないのです。当然将来価値の上がる企業に投資したいわけです。投資選別をいかにしていくか、それがBS、PL、CFだけでは本当の企業価値が把握できないという最近の動向なんですね。
これらの財務情報はあくまでも終わった、干したイカである。生きたイカではないというのが昨今の機関投資家の考え方なんです。干したイカが太っていたいいイカですね、というのはあるんですけど、今泳いでいるイカはどういうイカなのか。生きているイカは、経営者であり、人と組織なんですね。その泳いでいるイカの目がキラキラ輝いているのか、七色に光っているのかというのを知りたいのが機関投資家なんですよ。なので、御社の人的資本を開示して下さいと、機関投資家が一社一社くまなく会社を訪ねて全部教えてくださいって言うのは無理があるじゃないですか、それは不可能なので、それをちゃんとしたレポートとして開示してくださいと言っているんです。それによって、ダイベストメント(売り)か、インベストメント(買い)かを選別して決めているわけです。
D:干したイカとか生きているイカという言い方をするんですか?
N:この話ではよくそういう例えを使いますね。日本だとスルメと泳いでいるイカっていう言い方しますね。
D:以前、中川先生が世界最大の機関投資家ブラックロック社にヒアリングに行かれたと伺っていますが、その時もそういうお話があったのでしょうか?
N:そうですね、全部見るのは不可能で、CFOとの対話だけではなかなか、特にCFOに聞いても財務情報のCFとか、ROEとか、そういうことは説明されますけど、実際に今組織がどうなっているかということはCFOとの対話からはが出てこない。そこが知りたくても、1対1で話し合うのもそれなりに時間かかりますので、すべての企業に人的資本を開示してもらえれば知ることができる。
今の時点では、企業に対しどのような情報を出しなさいという厳密な枠組みは決められていません。割とそこは企業の自由に任されています。これは米国でもそうです。企業の自由で良いと、強いところだけアピールしても結構ですよと。ただ、あまりにも通り一遍のことしか書いていないのでは意味がないし、しっかりチェックもされています。レポート上のワード数も見ているみたいなんですね、1000ワードしかない企業は人的資本開示に興味がないと判断される場合もあるようです。ワーディングが少ない=興味がないと投資家はみるわけです。
そして大事なことは、各企業の中期経営戦略や重要課題(マテリアリティ)を達成するための人的資本の観点から開示すること。それが最重要事項です。投資家はいかにここが良い会社なのか、そうでないのかを常にあらゆる情報にアクセスして判断しているわけで、それはなぜかというと資金の出し手である委託者というステークホルダーがいるからですね。単なるほかの会社と同じことをしているという横並びの開示であれば、本当に意味がないです。なぜならば真似ができるケイパビリティと判断されるから。真似ができるどころか、他社と同じことをやっていても、競争優位にはなりえませんよね。
人材版伊藤レポートを読み解く:個人の能力と組織能力の両方が重要
D:人的資本開示に関連して、最近話題になっている伊藤邦雄先生のレポートについてもお伺いしたいんですが、特に、このレポートの重要なポイントだったり、中川先生はこのレポートについてどんな風に感じていらっしゃるか教えてください。
N:伊藤先生のレポートは、見方を”人的資源”から”人的資本”に変えたということがものすごく大きい功績だと考えています。従来、英語でヒューマンリソースマネジメントという言い方がされていましたが、伊藤レポートではヒューマンキャピタルという表現を使っています。欧米の人的資本開示の概念をいち早く日本に導入したということですね。共通言語としての人的資本を日本に導入し、マルチステークホルダー間の対話のギャップを埋めていく提言をされました。キャピタルとは投資してその価値が上がっていく、人的資本とは未来に対する投資なんだっていうことです。例えばCFOであれば、いわゆる人件費をコストとして管理していて、ここを引き下げれば利益があがっていくと考えるんですね。そういう形で見るか、それともここはROI(投資利益率)として見るか、それで全く見方が違うわけですよ。それが伊藤先生の功績として一番大きいポイントだと思います。
これをROI、インベストメントだと見た時に、じゃあ、全員に対して同じようにインベストメントするのが得策なのかそうでないのか、これは会社によっても違いますけれども、その会社の中期経営計画、10年ビジョンを達成するためには今後、こういう人材が必要で、こういう人材に近い人にもっと投資をしたい、こういう人材になってもらいたいから、リスキルなどの投資をしたいと、投資対効果を常に考える戦略に変わっていくわけです。そうしますとオペレーションのコストという考え方ではなくなってきますので、当然取締役会、経営者、CFOがもっと人への投資に重点を置こうとイニシアチブをとっていくわけです。
 会社と従業員の関係も、雇用している・雇用されているという関係よりは、あなたにこれだけ期待しているんですよということの対話、価値創造を一緒にしていこうという対話に変わっていく。一人一人のスキルの向上が非常に重要になるんですね。個の自立、お互いに切磋琢磨しながら成長していって、一人の成長、組織の成長が会社の成長につながるというまさに正のベクトルにつながっていくわけです。あなたはうちの会社の雇用者、使用人という関係よりは、お互いが自立した立場でお互いエンゲージメント(双方が信頼をベースに、双方の成長に貢献したいと思っている状態)で成り立っている関係になっていく。一昔前のお互いに従属、親と子の関係、お殿様と武士の関係ではないんですね。お互いが個と個の自立、本人の自律がエンゲージメントという対等な信頼関係で結ばれていることが重要です。
会社と従業員の関係も、雇用している・雇用されているという関係よりは、あなたにこれだけ期待しているんですよということの対話、価値創造を一緒にしていこうという対話に変わっていく。一人一人のスキルの向上が非常に重要になるんですね。個の自立、お互いに切磋琢磨しながら成長していって、一人の成長、組織の成長が会社の成長につながるというまさに正のベクトルにつながっていくわけです。あなたはうちの会社の雇用者、使用人という関係よりは、お互いが自立した立場でお互いエンゲージメント(双方が信頼をベースに、双方の成長に貢献したいと思っている状態)で成り立っている関係になっていく。一昔前のお互いに従属、親と子の関係、お殿様と武士の関係ではないんですね。お互いが個と個の自立、本人の自律がエンゲージメントという対等な信頼関係で結ばれていることが重要です。
D:他には伊藤レポートで注目すべきことはあるんでしょうか?最後は企業文化に落とし込んでいくような感じですが。
N:先ほども申し上げましたが、伊藤レポートで導入された”人的資本”という概念は、人は、適切な機会を与え、やりがいのある働き方ができる環境を提供すれば、成長し、価値創造の担い手になる。つまり価値が上がる。価値が上下するのならば、資源ではなく資本だ。であれば、マネジメントの方向性も、人の管理ではなく、人の成長を通じた「価値創造」へ変え、人に投じる資金は価値創造へ向けた「投資」と考えるべきだ。このように、人を「資本」と位置付けて、いかに価値を高める組織を整備するか、という視点が提言されています。
そして、人的資本の価値は、必ずしも社員個人の能力ばかりではなく、組織としての経営戦略にそって業務を遂行する能力や、新しいビジネスモデルへの適応力も含まれています。これが私が先ほど申し上げた模倣困難な”ケイパビリティ”とも言い換えられます。そして、経営戦略と人事戦略との連動、事業ポートフォリオの見直しと人の適所適材配置、機関投資家との対話の推進も注目すべき点です。
終身雇用で、組織の決定やルールの遵守を求められることで、社員の自律性や自立性が削がれ、かつ、長期雇用のため自分の出すエネルギーを平準化して全力を尽くさなくなる。私が「悪性安心感」と呼ぶものですが、そのような空気がまん延していることへの警告。「メンバーシップ雇用型」の企業文化の負の影響が出てきている企業文化からの刷新を提言しています。
人的資本の“戦略的な”開示とは?・・・ストーリー自体がケイパビリティ
D:そのような背景を踏まえて戦略的に開示していくとなった時に重要なポイント、まずは開示する一つの目的としてダイベストメントを避けることが重要なんだというお話がありましたが、ダイベストメントを避けようとしたら特にどんなことを開示していくのが大切なんでしょうか。開示をされようとしている会社さんはどういうところに重点を置いたらいいのかをお話ください。
N:企業は生き残らないと価値がない。生き残りが必要なんですね。そういう中で10年ビジョンですとか、中期経営計画、リスクと機会の重要課題(マテリアリティ)などを議論しながら作って資本市場に開示しているわけです。人的資本のイベントはそれらとアラインしているのか、そういう流れに沿っているのか?経営戦略や重要課題(マテリアリティ)と全然違う他社と横並びの人事施策をやっていても意味がないんですね。それはやっているだけ。あくまでもその10年ビジョン、中期経営計画、リスクと機会の重要課題(マテリアリティ)のKPIを達成するためにこの人的資本戦略が、人事施策、ダイバーシティ戦略があるんだと、そことアラインしているかどうか、その一貫性を市場に対しに見せつける必要があるわけですね、パラパラと今やっている施策を無関係に羅列するのではなくて、「この施策は中期経営計画のこの部分を達成するための施策」とか、それを書くことで、投資家には、経営戦略を達成するためにこういう人をこういう風に使って人に対して投資しているんだなとわかる。そのストーリーが明白にわかること。これが大事で、だから他の企業と同じような人事施策とかダイバーシティ施策をやっているとすれば、それは戦略論から言えばありえないんです。その企業独自の施策があるはずなので、その施策をもって成功した人的資本というのが模倣困難な”ケイパビリティ”なんです。
D:そのストーリーは企業ごとに違っていて、そのあたりを伝えていくというのが大事ということですね。
N:その会社の経営戦略ストーリーにあっているかどうか、目標を達成するためのストーリーにあっているかどうか、そのための人的資本への投資なのです。ですからそのストーリーは各社固有のはずです。これをもって、当社は人を採用をし、これをもって育成し、こう評価し、これをもって一人一人のエンゲージメントがあって、これをもって人と組織の成長につながり、企業のパフォーマンスにつながっているんだっていう一連の流れのストーリーが描けているか、そのストーリーも”ケイパビリティ”です。
 D:それはステキな言葉ですね。ストーリー自体がケイパビリティだと。
D:それはステキな言葉ですね。ストーリー自体がケイパビリティだと。
N:まるきり同じストーリーってあり得ない。もしあったとしたら、それは毒にも薬もならない情報開示です。人を大切にする、自然との調和、従業員の生活向上とか。そういう3点セット並べてるだけじゃ意味はない。もちろんそれは大事なんですけど、じゃあなんでそれが当社の10年ビジョンにつながっているのか、当社の中期経営計画達成に寄与しているのか、重要課題(マテリアリティ)により社会課題解決につながっているのかを、マルチステークホルダーとの対話で明白に話せるのかどうか。株式会社とは、NPOとか、コレクティブワーカーじゃないんで、ちゃんとした目的を達成するためには、資本市場に責任があるわけですから、開示しなければいけないんですね。そういう独自のストーリーのある会社というのは模倣困難な”ケイパビリティ”を持っているので競争優位があるということが明らかですから、機関投資家からはインベストをされるわけです。他社との比較で、それがないと、売り、ダイベストメントなんですね。個人の売りよりも、機関投資家の売りはものすごい額の大きいところなんで、経営者にとってはかなりまずいですよね。一度株価が落ちてしまうとエクイティファイナンス(資本市場からの直接金融)とかもできなくなり、被買収リスクも高まるので、企業の体力が急速に弱まってしまいます。
具体的かつわかりやすい開示のポイントや開示に向けたロードマップ
D:大きなストーリーをしっかり固めるのが重要なのはわかりましたがそのうえで、もう少し細かいところではどんなところがポイントになりそうなんでしょうか。
N:これは、意外に日本企業では重視していないかもしれないですが、人権ですね。これはサスティナビリティ、サプライチェーンの中での人権です。その次はD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)。トヨタモーターズコーポレーションが去年NYSEに出した英語の統合レポート見て頂いたらわかるんですけど、一番ページを割いているのがこの人権とD&Iなんですね。すなわち、ページを割く=そこに力を入れていますという決意表明なんです。D&Iというと、また女性の話ですかってなっちゃうんですけど、そうではないんですね。国が言っているとか、CSRだからではなくて、企業の生き残りをかけた時に、何がこれから起こるかわからないVUCA(将来予測が困難な時代)の世の中では、組織の中に多様性を持たせることが一番強い。
いかなる環境、いかなる顧客に対しても対応できるのは組織の中に多様性を持っているかどうかなんです。それがレジリエンス、頑健性、生き残りなので、成長のサスティナビリティなわけです。企業が生き残るために、D&Iは重要なんですね。けして、このCSRとか法令順守のためではないんです。
D:SCMの中での人権、そしてD&Iの話、他には重要なポイントありますでしょうか?
N:日本が得意な点でいうと安全と衛生、これは特に工場を持つ製造業でですね。安全教育は強いと思いますので、トヨタさんもヘルス&セイフティとして大きく書いていますね。健康経営も重要です。COVID-19などもあり、従業員の心身の健康ということが伊藤レポートでも言われていますけど、心身の健康があってこそのエンゲージメントがありますので、そういったところも重要になってきます。
D:中川先生がこれまでにご覧になった統合レポートにおいて、よく書けているなというものはどんなものがありますか?それはどのような点で優れているのでしょうか。
N:海外のレポートをみますと、欧州ではドイツ銀行はやはり良くできていると思います。ただ、102ページもHRレポートに割いているんで読むにはいいですけど真似するにはあまりにハードルが高い。次に良いなと思ったのはサムスン。サムスンはHRレポートを42ページ書いています。中身は絵が描いてあったり、図が入っていて非常にわかりやすいです。ご存じない方も多いかもしれませんが、サムスンはトヨタ自動車よりも時価総額が大きいんですよね。それぐらい大きい企業ですが、トヨタと違うところは、トヨタは食物連鎖の一番上にいて、サムスンは食物連鎖の真ん中にいますから、開示内容によっては、米企業から調達で外されたりするリスクもある。そういう点で非常に鍛えられているので完成度の高いHRレポートができているのかなと思います。とはいえ、私が見た中で真似できそうなのは、トヨタモーターズコーポレーションの2021年に出された英語レポートですね。ソサエティ(S)の内容が一番お手本となりそうなものかなと思っています。昨年のものは英語しかなかったですが、今回はおそらく日本語でも出されると思います。トヨタさんぽい内容でいえば、先ほども話しましたが、Safety、あとはQualityも書かれていますが、最も紙幅を割いていたのは人権とD&Iでした。
トヨタモーターズコーポレーションをお手本にするにしても、どれくらいまで開示したらいいんだろう、どこに力点を置いたらいいんだろうというのは各社、優先順位はあると思います。それぞれの会社さんで、中期経営計画およびリスクと機会の重要課題(マテリアリティ)を作っていらっしゃると思いますので、必ずそれらと目的が一致するようにしてください。当社はデジタルを活用したビジネスを新規に行っていくということであれば、デジタル人材を増やす必要がある、そうであればどうしていくのか、外から採用ってそんなに簡単じゃないですよね。
あのAmazonですら簡単じゃないと言って社内でリスキルトレーニングをやっている。倉庫の人にリスキルをして、データサイエンスとスキルを取得してもらう。ドイツ銀行ではフィンテック化に舵を取っているため全員にデジタルスキルのオンラインのトレーニングをして、デジタルが全くできない人だと居場所がなくなるとまで公言しています。銀行はこの先、FINTECHが主流になるからです。
デジタル人材を育てるということも、D&Iの中の一つとして、個人の中のダイバーシティに分類されます。リスキルとは、従来型のスキルを所有する人材だけではなかなか達成することが難しい中期経営計画を達成するためには、こういう新しいスキルを持つ人財を増やしていくんだ、ということ。リスキルは伊藤レポートでも、重要なこととして書かれています。なぜならば外から採用できれば一番いいですけど、そんなに簡単じゃないからです。
D:今後こういうレポートを作ろうと思われている会社は、開示のタイミングを考慮すると、何月ごろにどんな動きをして、何月までに何を作るみたいなスケジュール感で動いていくと一番理想的でしょうか。
N:会計年度が1-12月期の企業は、決算書の最終的なものを2月の中旬に出して3月に株主総会を行います。それで、一年の総決算が終わるわけです。その結果がこうだった、その結果に対して未来はこうしていくよという意気込みを示す統合レポートを、株主総会から遅滞なく、一か月ちょっとくらい、5月の初めくらいに出すというのが理想的なんですね。日本に多い、4-3月期では、3月決算、5月に決算書を出して6月に株主総会、8月はじめ、お盆の前くらいまでに統合レポートを出すのが遅滞なく、他社に後れを取ることなく開示という点で理想です。
D:それに合わせていつ頃何をしていくかというのを社内で決めていただいて動いていくのが大事ということですね。
N:そうですね。また、社内の方が固有のストーリーを理解して書ける場合はよいですが、ストーリーの書き方がわからない場合や戦略とのアラインがよくわからないような場合には、私どものような外部の人間がヒアリングさせていただいて中期経営計画と重要課題(マテリアリティ)を達成するためのストーリー作りをお手伝いすることもあります。投資家から、がっかりされるのは避けたいですよね。ESGのなかの、特にEの部分は気候変動のところは計算式もあるので、それを使っていただく。Sのところはまだどう書いていいかわからないという方が多いものですから、Sの部分をサスティナビリティ、アジアのサプライチェーンの人権の透明性という多少センシティブなパートのところも含めて、ヒアリングさせていただいたうえで、こういう書き方もできますよというアドバイスを含めたお手伝いもしています。そうすれば作成に半年もかからないですね。2,3ヶ月でできるかなと思います。
D:自社の“ケイパビリティ”をきちんとアピールしていくことが今後ますます重要になるということですね。よく理解できました。ありがとうございました。
